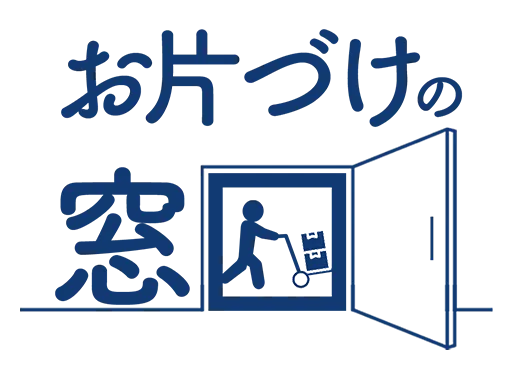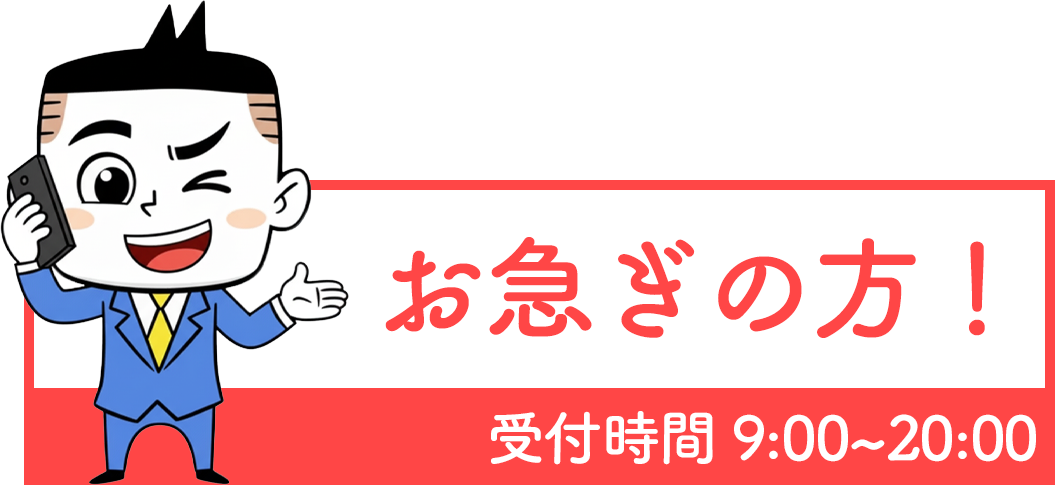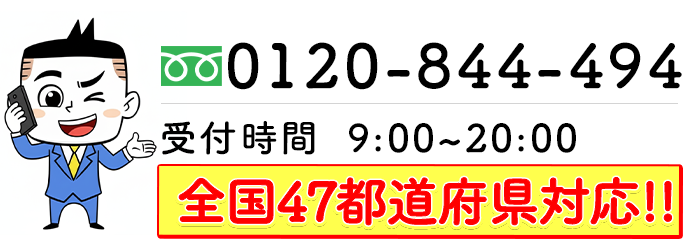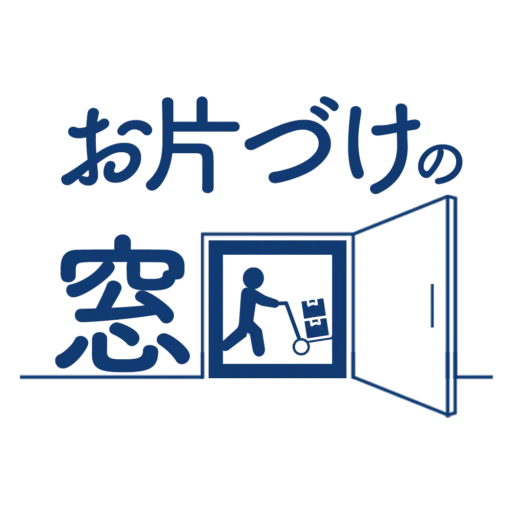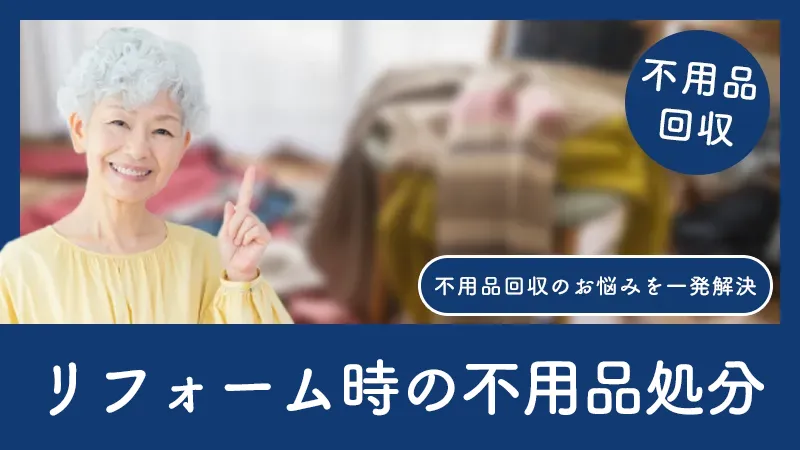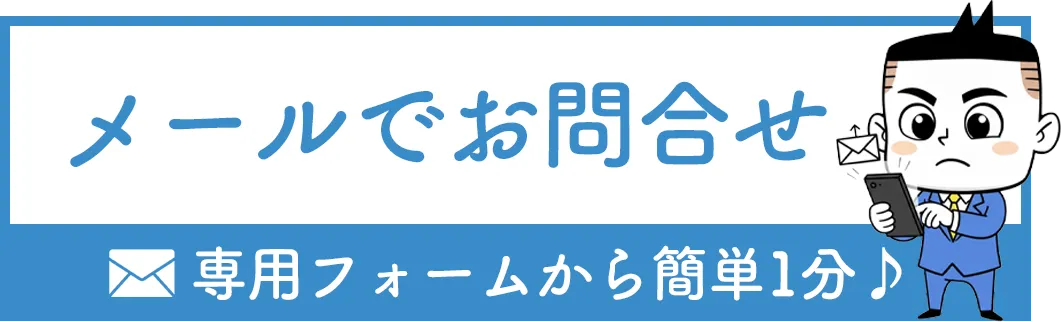編集長
私自身、過去に何度も不用品回収サービスに助けられた
元・ヘビーユーザーです。
その実体験から、いざという時に頼れる『利用者目線の情報』をお届けするという
理念を掲げ、実体験に基づいた情報をお届けします!
リフォームで失敗しないための「不用品処分」パーフェクトガイド
~計画・業者選びからコスト削減、トラブル対策まで全知識~
新しくなるキッチンに胸を躍らせ、どんな壁紙にしようかとパートナーと笑い合う。リフォームや建て替えが決まった瞬間の、あの高揚感は本当に特別なものですよね。
しかし、その興奮が少し落ち着いた頃、ふと現実的な問題が目の前に立ちはだかります。
そう、「この家にある、膨大なモノたちを、一体どうするんだ?」という問題です。
開かずの間の押し入れ、子供が昔使っていた勉強机、何年も電源を入れていないオーディオセット、そしてベランダの隅で忘れられた植木鉢の山…。それらが一斉に「私をどうするんだ」と語りかけてくるような、途方もないプレッシャー。
私も数年前に自宅をリフォームした際、そのプレッシャーで一度は思考停止になりました。仕事で忙しい平日は何もできず、週末になるたびに溜息をつく。そんな私が、試行錯誤の末にたどり着いた「失敗しない進め方」。
この記事は、単なるノウハウ集ではありません。リフォームという大きな節目を最高の形で迎えるために、私が経験から掴み取った、実践的な知識と段取りのすべてです。
第1章:方針決定編 – 誰に、どう頼むか?

不用品の山を前にして、多くの人が「まず、捨てなきゃ!」と、目の前の段ボールに手を伸ばしがちです。しかし、お待ちください。その行動が、後々の大きな後悔に繋がることがあります。
片付けを始める前に、たった一つ、しかし最も重要な決定をしなければなりません。それは、「不用品処分を何処に頼むか?」を決めることです。
この最初の選択が、あなたの予算、スケジュール、そして精神的な負担を大きく左右します。選択肢は、大きく分けて4つ。それぞれのメリット・デメリットを、私の実体験も交えながら見ていきましょう。
このノウハウはリフォーム不用品処分でも、建て替え不用品処分でも使えます!
1-1. 依頼先の4つの選択肢とメリット・デメリット
1-1-1. リフォーム会社への一括依頼
これは、忙しい会社員にとって最も魅力的に映る選択肢でしょう。「家のことは全部お任せします」という安心感。リフォームの打ち合わせのついでに、「不用品もまとめてお願いします」の一言で済む手軽さ。私も最初は、迷わずこれを選ぼうとしていました。
- メリット:
- とにかく楽。 業者を探す手間も、工事との日程調整も不要。窓口が一本化されるのは絶大な魅力です。
- 工事と連携がスムーズ。解体で出る廃材と、家財の不用品を同時に運び出してくれることも。
- デメリット:
- 費用が割高になる可能性が高い。 リフォーム会社は処分を専門業者に下請けに出すため、中間マージンが上乗せされるのが一般的です。
- 費用の内訳が不透明になりがち。 見積書に「残置物処分費 一式 〇〇円」としか書かれておらず、何にいくらかかったのか全く分からない、というケースは本当によくあります。
私の友人がまさにこのケースでした。最終的な請求書を見て、「不用品処分費 35万円」という文字に愕然としたそうです。もちろん量は多かったそうですが、相見積もりを取らなかったため、それが高いのか安いのか判断できず、ただ支払うしかなかった、と悔やんでいました。
【結論】手間を最優先し、費用は気にしない、という方には良い選択肢。しかし、少しでもコストを意識するなら、即決は禁物です。
1-1-2. 専門の不用品回収業者への直接依頼
次に、自分で専門の業者を探して直接依頼するパターンです。リフォーム会社を通さない分、コストを抑えられる可能性があります。
- メリット:
- 費用を抑えられる可能性。 相見積もりを取ることで、適正価格で信頼できる業者を選べます。
- 買取など専門的なサービスを選べる。 価値のある品を買い取ってもらうことで、処分費用をさらに安くできる可能性があります。
- サービス内容が明確。
- デメリット:
- 業者を探し、見極める手間がかかる。 これが最大の難関です。
- 悪徳業者に遭遇するリスクがある。 私が以前「2トントラック積み放題」の記事で書いたように、「無料回収」をうたったり、当日になって高額な追加料金を請求したりする悪質な業者が残念ながら存在します。
【結論】費用とサービス内容にこだわりたい、情報収集を厭わないという方におすすめ。ただし、業者選びという「目利き」が求められます。(この業者選びの具体的な方法は、後の章で徹底的に解説しますのでご安心ください)
大量の不用品回収についてはこちらの記事が参考になります!
1-1-3. 自治体サービスの最大限活用
「とにかく1円でも安く!」と考えるなら、自治体の粗大ごみ収集やクリーンセンターへの自己搬入をフル活用する方法があります。私もリフォーム時、「やれるところまで自分でやってみよう」と挑戦しました。
- メリット:
- 費用が圧倒的に安い。 数百円〜数千円で済む品目が多く、コスト面では最強の選択肢です。
- デメリット:
- 尋常ではない手間と時間がかかる。 粗大ごみシールの購入、収集の予約、指定場所までの搬出…これを数十個の品物で繰り返すのは想像を絶する作業です。
- 運搬手段が必要。 クリーンセンターに持ち込むにも、車、できれば軽トラックが必要です。
- 対象外の品物が多い。 家電リサイクル法対象品(テレビ、冷蔵庫等)やPC、土、石などは回収してくれません。
正直に告白します。私は週末の2日間をすべて費やし、軽トラックをレンタルしてクリーンセンターを2往復しました。結果、節約できたのはおそらく2〜3万円。しかし失ったのは、家族と過ごすはずだった貴重な休日と、その後3日間続いたひどい腰痛でした。「時は金なり」を痛感した瞬間です。
【結論】体力と時間に絶対の自信があり、処分する品物が少ない場合に限定される「最終手段」と心得ましょう。
1-1-4. 上記を組み合わせるハイブリッド型
そして、私が最終的にたどり着いた、最も賢いと確信しているのがこの方法です。
- メリット:
- 手間と費用のバランスを最適化できる。 それぞれの選択肢の「良いとこ取り」が可能です。
- 満足度が最も高い。 自分で全体をコントロールし、納得感を持って処分を進められます。
- デメリット:
- 最初に計画を立てる必要がある。 とはいえ、その手間をかける価値は十分にあります。
具体的には、以下のように役割分担をするイメージです。
- 【売る】 価値のありそうな本・服・家電 → 専門の買取業者やフリマアプリで売却。
- 【専門業者に任せる】 大型家具・処分が面倒なモノ・買取不可品 → 信頼できる不用品回収業者にまとめて依頼。
- 【自分で捨てる】 細かいゴミ・衣類など → 自治体の通常ゴミや資源ごみでコツコツ出す。
【結論】リフォームの不用品処分を成功させたいすべての人に、私が最も強くおすすめする最適解です。
さあ、4つの選択肢が見えてきました。 あなたが今、どの選択肢に最も心惹かれているでしょうか?この方針を決めることが、すべての始まりです。
1-2. 業者選びで失敗しないためのチェックリスト
さて、4つの選択肢の中から、ご自身の心づもりは決まってきたでしょうか。 「やっぱり手軽なリフォーム会社かな」「いや、コストを考えて専門業者を探そう」――どちらの道を選ぶにせよ、この先のステップを間違えると、せっかくの方針が台無しになりかねません。
ここからは、あなたが「良いパートナー」を見極めるための、具体的な質問リストをお渡しします。このリストさえあれば、もう何も恐れることはありません。
1-2-1. リフォーム会社に確認すべきこと
リフォーム会社への一括依頼は、例えるなら「料金のわからないおまかせコース」を頼むようなもの。安心しきって「お願いします」と一言で済ませてしまう前に、必ず以下の3つの質問を、担当者に投げかけてみてください。誠実な会社かどうかは、この質問への答え方で9割わかります。
- 質問①:「リフォーム時の不用品処分費の見積もりは、『一式』ではなく、内訳をいただけますか?」
これを渋る会社は、まず警戒してください。「一式」という言葉は、不透明な料金の温床です。誠実な会社であれば、少なくとも「トラックのサイズ(例:2トンショート)」「作業員の人数」「おおよその立米(㎥)単価」など、料金の根拠を示してくれるはずです。この質問は、「私たちは素人ではありませんよ」という意思表示にもなり、相手に緊張感を持たせる効果があります。 - 質問②:「作業されるのは提携業者さんですか?その会社名と、『一般廃棄物収集運搬業許可』を持っているか教えてください」
これが、最も重要です。 実は、家庭から出るごみ(不用品)を有料で収集・運搬するには、市区町村が発行する「一般廃棄物収集運搬業許可」が絶対に必要です。 リフォーム会社自身がこの許可を持っているケースは稀で、ほとんどが提携業者に再委託します。その“孫請け”業者が無許可だった場合、あなたの不用品が不法投棄されるリスクが一気に高まります。そして最悪の場合、依頼主であるあなたも責任を問われる可能性があるのです。「ええっと…」と言葉を濁すようなら、その話は一度持ち帰って検討し直すべきです。 - 質問③:「買取サービスは可能ですか?もし可能な場合、専門の方が査定されますか?」
まだ使える家電や、価値のありそうな家具。それらを単なる「ゴミ」として扱ってしまうのは、あまりにもったいない話です。この質問をすることで、リフォーム会社が不用品を「価値ある資産」として見てくれる可能性があるか、その姿勢を測ることができます。「うちの作業員が見て、値段がつけば…」といった曖昧な返事であれば、本格的な査定は期待できません。その場合は、やはり自分で専門の買取業者を探す方が賢明です。
これらの質問に、笑顔で、そして明確に答えてくれる担当者であれば、信頼できるパートナーである可能性は高いでしょう。
1-2-2. 専門業者選びの絶対条件(許可・保険)
次に、ご自身で専門業者を探す道を選んだ、勇敢なあなたへ。 ネットで検索すると、無数の業者が「業界最安値!」とアピールしていて、どこを信じればいいか分からなくなりますよね。でも、ご安心ください。見るべきポイントは、たったの2つ。この「2つの絶対条件」を満たさない業者は、どんなに安くても、どんなに感じが良くても、候補から外してください。
- 絶対条件①:『一般廃棄物収集運搬業許可』を持っている
先ほども触れましたが、これは絶対です。「産業廃棄物」や「古物商」の許可だけでは、家庭の不用品は運べません。違法です。 では、どうやって確認するか? 優良業者は、必ず自社のウェブサイトの「会社概要」などに、「許可番号:〇〇市 一般廃棄物収集運搬業 第XXXX号」といった形で明記しています。これが見当たらない業者は、その時点で選択肢から外しましょう。 - 絶対条件②:『損害賠償責任保険』に加入している
これは、万が一の事故への「誠意の証」です。 不用品の搬出は、常に家を傷つけるリスクと隣り合わせです。壁紙にタンスの角を擦ってしまう、マンションの共用廊下の床に傷をつける、最悪の場合、通行人に怪我をさせてしまう…。考えたくありませんが、可能性はゼロではありません。 私がリフォームを決意する前、同じマンションの別の方が、格安業者に依頼して大変な目に遭っていました。作業員が洗濯機を落としてしまい、エントランスの床タイルを割ってしまったのです。しかし、その業者は保険に入っておらず、「払えない」の一点張り。結局、その方は管理組合との間で板挟みになり、大変な心労を抱えていました。 「保険に加入していますか?」の一言が、あなたとあなたの家、そしてご近所さんとの関係を守る命綱になります。
不用品回収業者の選び方はこちらの記事をご参照ください
「許可」と「保険」。 この2つの盾さえあれば、悪徳業者に遭遇する確率は限りなくゼロに近づきます。
さあ、これで誰に頼むべきか、そしてどうやって優良なパートナーを見極めるか、その武器は手に入りました。 いよいよ次の章では、具体的なアクションプラン、「いつ、何をすべきか?」という計画の立て方に進みます。ここを制する者が、リフォームの成功を制するのです。
第2章:計画編 – いつ、何をすべきか?

パートナー選びという、最も重要な第一歩を踏み出したあなた。 しかし、どんなに優秀なパートナーを選んだとしても、「いつ、何をすべきか」という計画がなければいけません。
リフォーム前の片付けの最大の敵は、不用品の量そのものではありません。本当の敵は、「まだ時間がある」という油断と、刻一刻と迫る「工事開始日」というタイムリミットです。
私が自宅のリフォームに際して、最初に感じたのは絶望感でした。まるで、ゴールが見えないマラソンをいきなり走り始めたような感覚。「何から?」「どこから?」と、ただ時間だけが過ぎていく焦り。
その状況を打破できたのは、一枚の紙に簡単な年表のようなものを書き、「この日までに、これを終わらせる」という、具体的なマイルストーンを置いた時でした。 この章では、私が試行錯誤の末に作り上げた、パニックに陥ることなく、そして確実にゴールにたどり着くための「完璧なタイムスケジュール」を、あなたに授けます。
2-1. 時系列で見るタスクリスト
ここに示すスケジュールは、あくまで一つのモデルです。ですが、この流れに沿って進めるだけで、「やるべきこと」が明確になり、驚くほど心に余裕が生まれるはずです。
2-1-1. 【工事契約前〜3ヶ月前】 全体把握と仕分け開始
この時期は、いわば「偵察フェーズ」です。本格的な処分の前に、不用品の全体量を知り、残すモノを把握することが目的です。
- ① スマホ片手に、家中の「現状」を記録する まずは家の中の探偵になってください。普段は開けないクローゼットの奥、物置の隅々まで、すべてを開けてスマホで写真を撮りましょう。これは感傷に浸るためではありません。「我が家には、これだけのモノが、これだけの密度で存在する」という客観的な事実を、自分の目に焼き付けるための、最も効果的な方法です。
- ② 「家族会議」を開く これが意外と重要です。自分にとっては不要でも、家族にとっては大切な思い出の品、というケースは山ほどあります。後で「あれ、どこやったの!」という最悪の事態を避けるためにも、この段階で「残すモノ・捨てるモノ」の基準をすり合わせましょう。 ちなみに我が家では、「この1年間で一度も使わなかったモノ」を処分の第一候補とする、「1年ルール」を導入しました。最初は揉めましたが、このルールがあったおかげで、後の判断が驚くほどスムーズになりました。
- ③ 「4つのエリア」を作り、仕分けを始める 部屋の隅に、「残す」「売る・譲る」「捨てる」「保留」という4つのエリア(段ボールやビニールシートでOK)を作ります。そして、まずは本棚の古い雑誌やキッチンの賞味期限切れの食品など、感情を伴わない「明らかなゴミ」から捨て始めましょう。小さな成功体験が、この長い戦いを乗り切るための推進力になります。
2-1-2. 【着工2ヶ月〜1ヶ月前】 業者選定と相見積もり
偵察を終え、大まかな物量が把握できたら、いよいよ「実戦フェーズ」の準備です。プロの力を借りるための具体的なアクションを開始します。
- ① 業者候補のリストアップと連絡 第1章でお話しした知識を使い、候補となる業者を3社ほどリストアップし、見積もりの連絡を入れます。この時、「リフォームに伴う家一軒(あるいは〇部屋分)の片付けである」ことを明確に伝えましょう。
- ② 必ず「訪問見積もり」を依頼する 電話やメールだけの見積もりは、トラブルの元です。必ず家に来てもらい、物量を直接その目で確認してもらった上で、見積書を作成してもらいましょう。これは、料金の正確性を担保するだけでなく、担当者の人柄や専門知識を見る絶好の機会です。 私が必ずする質問は「この見積もりから、さらに安くする方法はありますか?」です。優良な業者の担当者なら、「この棚を事前に解体しておいてくだされば、作業代が〇円引けますよ」といった、プロならではの提案をしてくれます。
- ③ 買取業者への査定依頼 「売る・譲る」エリアに置いた品物も、このタイミングで専門の買取業者に出張査定を依頼します。不用品回収業者の中には買取を同時に行うところもありますが、骨董品や専門的な機材などは、それぞれ専門の業者に見てもらう方が高値がつく傾向にあります。
2-1-3. 【着工2週間前〜前日】 最終準備とゴミ出し
工事開始日が現実味を帯びてくるこの時期は、「最終追い込みフェーズ」です。
- ① 業者を1社に絞り、契約する 担当者の対応を比較し、依頼する業者を決定。作業日を確定させ、契約を交わします。
- ② 自治体ゴミの最終処分 自分で捨てると決めた粗大ごみや、溜まった資源ごみなどは、この期間に全て出し切ります。ゴミ収集車は、あなたの工事日程を待ってはくれません。計画的に処分を進めましょう。
- ③ 搬出経路の確保と、ご近所への挨拶 玄関からトラックまでの通路に、障害物がないか最終確認を。また、前日か前々日には、「〇日の〇時頃、不用品の搬出でご迷惑をおかけします」と、両隣とお向かいさん、階下のお宅くらいには一言声をかけておきましょう。この一言が、無用なトラブルを防ぐ最高のお守りになります。
2-1-4. 【搬出当日】 立ち会いのポイント
ついに迎えた「リフォームの日」。この日あなたがすべきことは、ただ一つ。「最高の現場監督」になることです。
- ① 必ず立ち会い、作業前に最終打ち合わせ これが鉄則です。作業開始前にリーダーの方と、「これは残すモノ、これは持っていくモノ」という最終確認を、指差しをしながら行ってください。 私の知人はこれを怠ったため、思い出の詰まった家族写真の箱を、誤って持っていかれてしまいました。取り返しのつかない後悔をしないためにも、最初の5分の打ち合わせを惜しまないでください。
- ② 指示を出す人間を一人に絞る 夫婦であれこれ指示を出すと、現場が混乱します。「今日の監督は夫(妻)」と決め、指示系統を一本化しましょう。
- ③ 全て運び出されたことを確認してから、精算する 作業が完了したら、空になった各部屋を回り、運び忘れがないか、壁や床に傷がついていないかを確認します。全てを確認し、納得した上で、料金を支払い、必ず領収書を受け取ってください。
お疲れ様でした。 このスケジュール通りに進めれば、当日慌てることなく、完璧に不用品を処分できるはずです。 家は、新しい姿に生まれ変わるための準備が整いました。
しかし、気になるのは、この一大プロジェクトにかかった「費用」ですよね。 次の章では、誰もが一番気になるお金の話、「費用の内訳」と「コストを極限まで抑えるテクニック」に、深く踏み込んでいきます。
第3章:予算編 – 費用はいくら?どう抑える?

リフォームの打ち合わせが進むと、数十万、数百万という金額が記載された見積書が、当たり前のようにテーブルに並びます。金銭感覚が少し麻痺してくる中で、つい見落とされがちなのが、この「不用品処分」にかかる費用です。
しかし、この費用は決して侮れません。計画段階で甘く見積もっていると、最終的に「こんなはずじゃなかった…」と、思わぬ出費に頭を抱えることになります。
この章は、単なる料金相場の解説ではありません。あなたが処分の費用を「コントロールする側」に回るための、戦略と実践テクニックです。私の財布も守ってくれた、この知識であなたの予算を徹底的に防衛しましょう。
3-1. 費用の仕組みを完全理解する
業者さんの提示する金額は、決して”言い値”で決まっているわけではありません。その裏には明確な算出ロジックが存在します。この仕組みを理解することこそ、料金で損をしないための第一歩です。
3-1-1. 料金の内訳(基本料金+追加料金)
不用品回収の料金は、多くの場合、以下のシンプルな方程式で成り立っています。
【基本料金(車両費+人件費+処分費)】 + 【オプション料金】 = 支払総額
- 車両費: いわゆるトラック代です。「軽トラ積み放題」「2トントラック積み放題」といったパック料金の基本部分は、主にこの車両費と、次の人件費で構成されています。
- 人件費: 作業スタッフの人件費です。「作業員2名まで」といった形で基本料金に含まれていることがほとんどです。
- 処分費: 回収した不用品を、業者が適切に処分するために支払う費用です。特に家電リサイクル法対象品などは、法律で定められたリサイクル料金が上乗せされます。
多くの「積み放題パック」は、この3つをコミコミにした、一見わかりやすい料金体系に見せているのです。しかし、本当に注意すべきは、この基本料金の「外」にあります。
3-1-2. 追加料金が発生する主なケース
私が初めて見積もりを取った時、基本料金の安さに驚き、喜んだのを覚えています。しかし、その見積書の隅に、小さな文字で書かれた「追加料金一覧」を見て、背筋が伸びました。これこそが、総額を大きく左右する“罠”になり得るのです。
- ① 階段料金: エレベーターのないマンションや、戸建ての2階からの搬出で発生します。「2階は+3,000円、3階は+6,000円」といった形で、階数に応じて加算されるのが一般的です。
- ② 特殊作業費: ピアノや金庫、大型の業務用冷蔵庫など、重量物や運び出しが困難なモノに適用されます。また、部屋の中で解体しないと出せない大型家具の「解体作業費」もここに含まれます。
- ③ 特定処分困難物: タイヤ、金庫、土、石、コンクリートブロック、消火器など、通常のルートでは処分が難しいモノには、特別な処分費用が加算されます。
- ④ 当日の追加依頼: 「これもついでに」と、見積もりにないモノを追加すれば、当然料金も追加されます。この積み重ねが、最終的に大きな金額差になるのです。
見積もりを取る際は、「私の家の場合、追加料金が発生する可能性はありますか?」と必ず確認し、考えられる項目を事前にすべて洗い出してもらうことが重要です。
3-2. コスト削減のための実践テクニック
さて、費用の仕組みがわかったら、いよいよ「攻めのコスト削減」です。ここからは、あなたの少しの手間が、数万円単位の節約に繋がる実践的なテクニックをご紹介します。
3-2-1. 買取サービスの賢い利用法
まず、思考を「捨てる」から「売る」に切り替えましょう。家の中は、隠れた資産の宝庫かもしれません。
- 基本戦略:専門分野ごとに、専門の業者を当たる 不用品回収業者も買取を行いますが、彼らはあくまで「処分のプロ」です。価値を正しく見極めてもらうなら、それぞれの分野のプロに頼むのが鉄則。古本はブックオフ、服はセカンドストリート、オーディオは専門買取店、といった具合に、処分の前に「買取業者めぐり」の期間を設けるのがおすすめです。
- 家電は「製造から5年以内」が一つの目安 特に国内大手メーカーの冷蔵庫、洗濯機、テレビなどは、製造から5年以内であれば、高確率で値段がつきます。逆に10年を過ぎると、買取はほぼ絶望的と考えましょう。
- 意外なモノに値段がつくことも 父の遺した古いウイスキー、昔使っていたブランドの食器、夫の趣味のゴルフセット。これらが、思わぬ高値で売れた経験があります。ダメ元でフリマアプリで相場を調べてみる、という一手間が、数万円の利益を生むことがあります。
3-2-2. 効果的な相見積もりの取り方
何度もお伝えしますが、これこそがコスト削減の王道にして最強の武器です。
- 「同じ条件」で比較する 3社から見積もりを取ったら、A社は税込み、B社は税抜き、C社はリサイクル料金込み…といった具合に、条件がバラバラなことがあります。そのまま金額だけを比較しても意味がありません。簡単な表でいいので、条件を横並びにして比較検討することが重要です。
- 交渉のカードとして使う これは少し上級テクニックですが、一番頼みたいと思っている本命の業者(B社)に、「実はA社さんからは、〇〇円という見積もりを頂いてまして…」と、正直に伝えてみるのも手です。もちろん無理な値引き要求は禁物ですが、誠実な業者であれば、「では、弊社は〇〇円で頑張ります」と、競合を意識した価格を再提示してくれる可能性があります。
3-2-3. 自分でできるコスト削減策
最後は、「自分の汗が最強のコストカッターになる」というお話です。
- ① 徹底的な分別 「これは燃えるゴミ、これは資源プラ、これは金属」といった具合に、家庭ごみレベルで構いませんので、分別を徹底しましょう。業者の作業時間が減れば、その分、人件費を圧縮できることに繋がります。
- ② 家具の解体 もしあなたが工具の扱いに慣れているなら、カラーボックスや木製ベッド、棚などを事前に解体しておきましょう。かさばる家具が「板」になることで、トラックの荷台スペースを大幅に節約できます。スペースが空けば、ワンサイズ下のトラックで済む可能性も出てきます。
- ③ 1階への運び出し 戸建てにお住まいの場合限定ですが、2階にある不用品をすべて1階に降ろしておくだけで、料金が変わることがあります。これは階段料金の削減に直結します。「1階にまとめておいたら、安くなりますか?」と、見積もり時にぜひ聞いてみてください。私もこれを実践し、5,000円の値引きをしてもらえた経験があります。
費用は、ただ請求されるものではありません。知識と工夫、そして少しの手間によって、あなた自身の手でコントロールできるものなのです。
さて、これで予算の管理も万全。 次の第4章では、これまで触れてこなかった、しかし誰もが一度は悩むであろう「あの品物」の処分方法…そう、仏壇や人形、庭の石といった、特殊なモノたちとの向き合い方について、詳しく解説していきます。
第4章:仕分け・処分編 – これ、どう捨てる?

計画を立て、予算を組み、パートナーとなる業者も見えてきた。大きな山は越えた…はずなのに、なぜか足が止まってしまう。目の前にある、たった一つの「モノ」が、とてつもなく大きく見える。
「この仏壇、どうすれば…」 「庭のこの石、まさか捨てられないなんて…」 「父の遺品に、どうしても手が付けられない…」
この章は、そんなあなたの心の声に答えるための、具体的な実践編です。これまで培った知識を総動員し、家の中に潜む一体一体の「ボスキャラ」を、確実に攻略していきましょう。
4-1. 【モノ別】処分方法ハンドブック
まずは、多くの家庭に共通する「定番の強敵」たちから。ここはスピード勝負です。
4-1-1. 大型家具・家電リサイクル品
- 大型家具(タンス、ソファ、ベッド): 第3章で触れた「解体」がここでも活きてきます。解体すれば運搬費(=人件費)と荷台スペースの節約に直結します。難しい場合でも、引き出しを抜いておくだけで、作業員の方はぐっと楽になります。
- 家電リサイクル品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン): これらは法律でリサイクルルートが定められています。業者に依頼する場合、必ず「リサイクル料金」と「収集運搬費」が見積もりに含まれているか確認しましょう。この料金は法律で定められているため、値切ることはできません。
大型の不用品に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご確認ください
4-1-2. 趣味の道具・コレクション類
ゴルフ、釣り、オーディオ、大量の蔵書…。これらは「価値があるはず」という思い込みが、処分を遅らせる原因になりがちです。
私の義父が遺した大量の釣り道具。一見するとお宝の山でしたが、専門の買取店に持ち込むと、値段がついたのは最新モデルのリール2つだけでした。残りの大量の竿や仕掛けは、残念ながら処分するしかありませんでした。 鉄則は「まず専門の買取店で価値を確定させる。値段がつかなかったモノは、思い切って処分する」です。 ダラダラと査定を続ける時間は、私たちにはありません。
4-1-3. 大量の衣類・食器・生活雑貨
一つ一つは小さくても、集まると巨大な山になるのがこのカテゴリー。 対処法はこの通りです。 ①ブランド品など売れそうなモノを抜き出す → ②まだ使えるモノはNPO団体などへ寄付 → ③残りはゴミとして処分、という流れを機械的に行いましょう。食器類は、海外へ寄付するルートもありますし、一部リサイクル業者が重さで買い取ってくれるケースもあります。
4-2. 精神的に捨てにくいモノとの向き合い方
ここからが、この章の本丸です。 これから向き合うのは、単なる「モノ」ではありません。思い出や祈り、愛情が宿った、あなたの人生の一部です。どうか、焦らないでください。一つ一つ、丁寧に向き合っていきましょう。
4-2-1. 仏壇・神棚・人形の供養
これらを「粗大ごみ」として出すことに、抵抗を感じるのは当然の感情です。 重要なのは「魂抜き(閉眼供養)」というステップを踏むことです。 私も祖父の家の仏壇を処分する際、菩提寺の住職にお願いして、家族みんなで手を合わせました。それは単なる処分ではなく、感謝を伝えて区切りをつけるための、大切な儀式でした。
選択肢は主に3つ。①菩提寺に相談する、②近所のお寺や神社に相談する、③供養まで請け負ってくれる専門の不用品回収業者に依頼する。 費用はかかりますが、心の負担を考えれば、必要な投資だと私は考えます。
4-2-2. 写真・アルバム・子供の作品
すべてを残すのは不可能。でも、すべてを捨てるのは辛すぎる。 このジレンマの解決策は「デジタル化」と「厳選」です。 私もリフォームの際、週末を使って古いアルバムをスキャナーで読み込みました。膨大な時間はかかりましたが、データとして残せたことで、「原本は処分しても、思い出は残る」と、自分を納得させることができました。子供の作品も、「各学年の代表作を1つだけ残す」というルールを決めて、あとは写真に撮ってから処分しました。
4-2-3. 故人の遺品
これが最も難しいかもしれません。特に、亡くなられてから日が浅い場合は、無理に進めるべきではありません。 まずは、無理のない範囲で「形見分け」を行いましょう。 そして、どうしても処分に踏み切れないモノは、「思い出ボックス」を一つだけ作り、そこに入る分だけは残す、という方法も有効です。 もし、ご自身やご家族だけでは精神的な負担が大きすぎる場合は、専門家である「遺品整理士」に相談するのも、決して特別なことではありません。
4-3. 【難易度高】特殊なモノの処分方法
最後に、知識がないと本当に行き詰ってしまう「ラスボス級」のアイテムたちです。
4-3-1. 屋外・庭のモノ(物置、庭石、土、植木)
心構え:屋外のモノは、屋内よりも処分費が高額になる。 私も見積もりを見て、腰を抜かしそうになりました。庭に置かれた、大人二人でやっと動かせるくらいの石。その撤去・処分費用が、なんと5万円。重機が必要になるためです。 物置も、解体費と中身の処分費が別にかかるケースがほとんど。そして、植木鉢の中の「土」。これはほとんどの自治体でゴミとして回収してくれません。これらは、造園業者や専門の回収業者に依頼するしかありません。屋外のモノは、必ず事前に専門業者に見積もりを取ってください。
4-3-2. 重量物・危険物(ピアノ、金庫、消火器)
鉄則:素人が手を出さない。 ピアノは、単に重いだけでなく、専門の技術で運び出さないと家を傷つけます。金庫は、中に何が入っているか確認する必要もあります。消火器は、破裂の危険もあるため、一般のゴミには絶対に出せません。 これらは全て、不用品回収業者の中でも「専門のスキルとルート」を持つ業者に依頼する必要があります。必ず見積もり時に「ピアノ(金庫)の処分もできますか?」と確認しましょう。
4-3-3. 古材・建具の売却可能性
最後に、希望の光です。あなたの家が古い日本家屋なら、ゴミだと思っていたモノが「宝物」に変わる可能性があります。 築50年以上の家にある、太い大黒柱や梁(はり)。美しい細工が施された欄間(らんま)や障子、デザインガラスの入った木製のドア。 これらは「古材(こざい)」として、高い価値を持つことがあります。「古材買取」専門の業者に連絡すれば、思わぬ高値で買い取ってくれるかもしれません。解体が始まる前に、一度査定を依頼してみる価値は十分にあります。
お疲れ様でした。 これで、あなたの家にある、ほぼ全てのモノに「進むべき道」を示すことができたはずです。 ゴールはもう目の前。最終章では、このプロジェクトの最終盤で起こりうる、予期せぬトラブルとその回避策について解説します。
第5章:対策編 – 起こりうるトラブルと回避策

ゴールテープは、もう目の前です。 あなたは計画を立て、パートナーを選び、目の前の不用品の山にも立ち向かってきました。しかし、どんなに完璧な準備をしても、リフォームという一大プロジェクトには、予期せぬ「落とし穴」が潜んでいることがあります。
この最終章は、あなたが最高の笑顔で新生活のスタートラインに立つための、「最後のお守り」です。これから挙げるトラブルは、決して他人事ではありません。実際に私の周りで起こった、あるいは私自身がヒヤリとした実話に基づいています。 しかし、ご安心ください。事前に知っておきさえすれば、そのすべては回避可能です。
5-1. 業者に関するトラブル
最も件数が多く、金銭的・精神的なダメージが大きいのが、業者とのトラブルです。しかし、これまでの章を読み込んできたあなたなら、もうその対策はほぼ身についているはずです。ここでは、最後の総仕上げとして、要点を再確認しましょう。
5-1-1. 不当な高額請求
「全部終わりました!…それで、追加で5万円になります」 作業がすべて完了し、ホッと一息ついた瞬間に、こんな言葉を告げられたらどうしますか? 私の同僚が、まさにこの手口の被害に遭いました。「見積もりにない処分品があった」「思ったより作業に時間がかかった」というのが、業者の言い分だったそうです。
回避策:
- 契約書(見積書)の「追加料金」に関する項目を、サインする前にもう一度読み返す。
- 作業当日、見積もりにない作業を依頼する際は、必ず「追加料金はいくらですか?」とその場で確認し、合意の上でお願いする。
- 精算時に納得できない請求があったら、その場で支払わず、詳細な説明を求める。
第1章、第3章でお伝えした「書面での確認」が、あなたを守る最強の盾になります。
5-1-2. 不法投棄(依頼主の責任問題)
「安くしますよ」という言葉に引かれて依頼した業者が、あなたの不用品を山奥に不法投棄。数日後、ゴミの中からあなたの名前が書かれた郵便物が見つかり、警察から連絡が来る…。
これは、冗談のような本当の話です。廃棄物処理法では、不法投棄を行った業者だけでなく、排出者(依頼主)にも「原状回復措置」などの責任が及ぶ可能性があります。知らなかった、では済まされないのです。
回避策:
- 業者が「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っているか、ウェブサイトや名刺で必ず確認する。(第1章の復習です)
- 極端に安い料金を提示する業者には、まず疑いの目を持つ。 適正な処分には、必ず相応のコストがかかります。
5-1-3. 作業中の家屋破損・事故
これも非常に多いトラブルです。新しくなるはずの家の壁や床が、不用品の搬出作業で傷だらけになってしまっては、本末転倒です。
回避策:
- 作業前に、搬出経路の壁や床の状態をスマホで撮影しておく。
- 業者が「損害賠償責任保険」に加入しているか確認する。(これも第1章の復習ですね)
- 作業開始前に、リーダーの方に「養生(ようじょう)はどこまでやっていただけますか?」と確認する。 (養生とは、壁や床を保護材で覆うことです)
誠実な業者は、こちらが何も言わなくても、搬出経路を丁寧に養生してくれます。これが、プロの仕事の証です。
5-2. 人間関係のトラブル
モノは片付いても、人の心がこじれてしまっては、最高の新生活は始まりません。最後に、最も繊細で、しかし最も大切な問題に触れておきましょう。
5-2-1. 家族・親族間の意見対立
「これは、お母さんの形見なのに!」 「いや、新しい家にはどう考えたって合わないよ!」
建て替え前の不用品処分は、家族の歴史と価値観がぶつかり合う、非常にデリケートな作業です。良かれと思って進めても、家族の誰かの「大切なモノ」を傷つけてしまうことがあります。
回避策:
- 最初に「仕分けの基本ルール」を家族全員で共有する。(我が家の「1年ルール」のようなものです)
- どうしても判断が分かれるモノのために、「保留ボックス」を用意し、結論を急がない。
- お互いに「聖域(サンクチュアリ)」を認める。「自分の趣味のモノには口出ししない」「お互い、どうしても捨てられないモノを3つだけ選ぶ」など、痛み分けのルールを作るのも有効です。
大切なのは、効率だけを求めないこと。片付けは、家族の歴史を再確認し、感謝を伝えるための時間でもあるのです。
5-2-2. ご近所への配慮と事前準備
リフォーム工事が始まる前から、ご近所との関係が悪化してしまったら…? 考えただけでも、憂鬱になりますよね。不用品の搬出作業は、あなたが思う以上に、騒音やホコリ、トラックの駐車などで、ご近所に迷惑をかける可能性があります。
回避策:
- 作業日の数日前に、簡単な挨拶状と粗品(タオルや洗剤など)を持って、ご挨拶に伺う。(第2章でお伝えした通りです)
- 業者に、トラックの駐車場所について、事前に近隣の迷惑にならない場所を確認してもらう。
- 作業が長引く場合は、夕方頃に一度「ご迷惑をおかけしております」と声をかける。
私がリフォームをした際、向かいに住む少し気難しそうなおじいさんが、挨拶に伺った時に「わざわざ律儀だねぇ。お互い様だよ」と、笑顔を見せてくれた時の安堵感は、今でも忘れられません。ほんの少しの心遣いが、あなたのこれからの暮らしを守ってくれるのです。
お疲れ様でした。 これで、あなたがリフォーム・建て替えの不用品処分という、巨大で複雑なプロジェクトを乗り切るための、すべての知識と武器、そして心構えは整いました。
目の前のモノの山は、単なるゴミではありません。 それは、あなたがこれまで生きてきた証であり、過去の暮らしそのものです。 それに感謝して、きちんと別れを告げ、新しい生活のためのスペースを空ける。不用品処分とは、そんな未来へ向かうための、神聖な儀式なのかもしれません。
この記事が、あなたの素晴らしい新生活への、確かな一歩となることを、心から願っています。