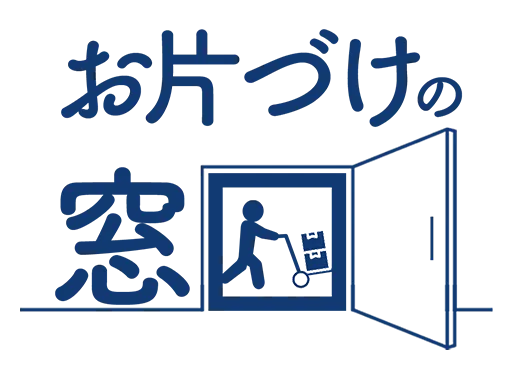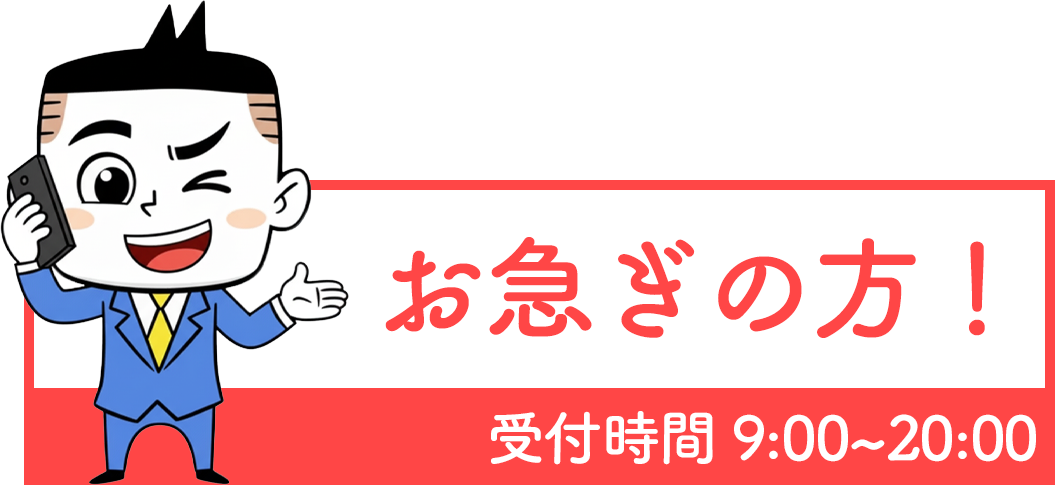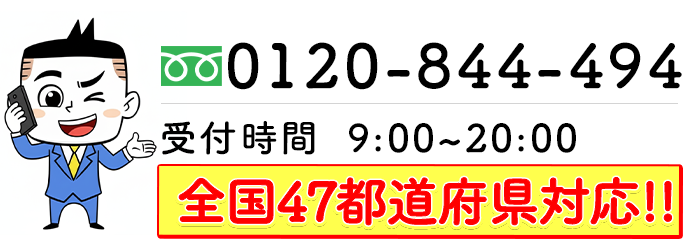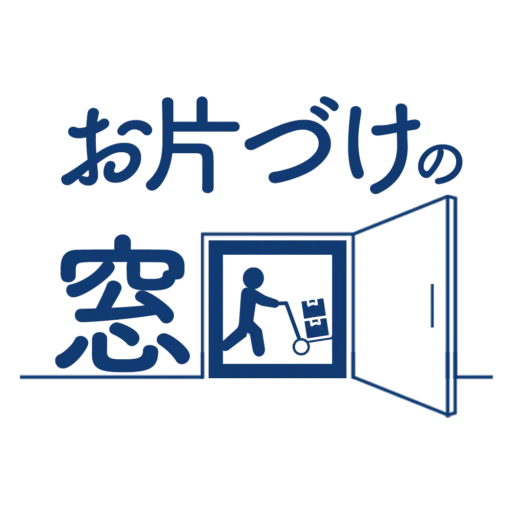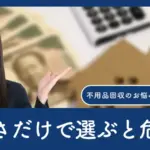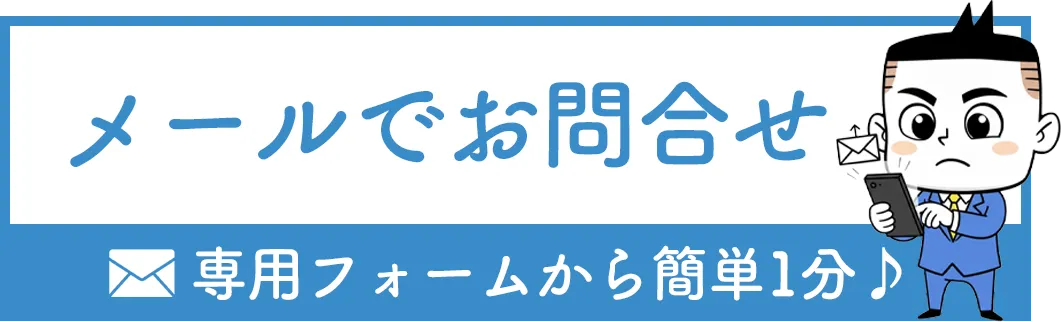編集長
私自身、過去に何度も不用品回収サービスに助けられた
元・ヘビーユーザーです。
その実体験から、いざという時に頼れる『利用者目線の情報』をお届けするという
理念を掲げ、実体験に基づいた情報をお届けします!
はじめに:オフィスの不用品処分は「事業活動」です
オフィスの移転、フロアの改装、年度末の大掃除――。事業活動を続けていると、古くなったデスクや椅子、壊れたPC、大量の書類など、様々な不用品が出てきます。
「業者を呼んで、全部まとめて持っていってもらえば終わりだろう」
もしあなたがそう考えているなら、少しだけお待ちください。実は、オフィス不用品回収は、家庭のゴミ捨てとは全く次元の異なる、企業の社会的責任が問われる「事業活動」なのです。
家庭のゴミ捨てとは全く違う!担当者が知るべきリスクとは

なぜ、それほどまでに違うのでしょうか。それは、オフィスから出る不用品の多くが、法律(廃棄物処理法)によって「産業廃棄物」として厳しく定義されているからです。
これを知らずに安易な業者選びをしてしまうと、担当者であるあなただけでなく、会社全体が以下のような深刻なリスクに晒される可能性があります。
- 【リスク1:法律違反】 無許可の業者に依頼し、その業者が不法投棄をした場合、依頼した側の企業(排出事業者)も罰せられる可能性があります。
- 【リスク2:情報漏洩】 PCのHDDや機密書類を不適切に処分したことで顧客情報や社内情報が漏洩し、会社の信用を根底から揺るがす大問題に発展するケースがあります。
- 【リスク3:金銭トラブル】 「無料回収」のはずが、作業後に高額な追加料金を請求されるなど、悪質な業者による金銭トラブルに巻き込まれることも少なくありません。
これらのリスクは、どれも「知らなかった」では済まされない、企業の存続に関わる重大な問題です。
しかし、ご安心ください。
この記事は、会社の不用品回収を初めて依頼する方や、これまでのやり方に少しでも不安を感じている方のために作られた「完全ガイドブック」です。
- 信頼できる業者の見極め方
- 処分費用を賢く抑えるコスト削減のテクニック
- 情報漏洩を防ぎ、法律を守るための具体的な注意点
など、担当者が知っておくべき全ての情報を、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたは数ある業者の中から自社にとって最適なパートナーを見つけ出し、あらゆるリスクを回避しながら、コストと手間を最小限に抑えたスムーズな事務所の不用品処分を実現できるはずです。
さあ、会社の信頼を守り、あなたの業務負担を軽くするための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
オフィスの引越しについても詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
第1章:まず知っておきたい「オフィス不用品」の基礎知識
不用品回収業者へ連絡する前に、まずは基本となる知識を身につけましょう。特に「産業廃棄物」についての理解は、担当者として自分と会社を守るために不可欠です。
1-1. なぜ専門業者が必要?「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違い

家庭から出るゴミ(一般廃棄物)は、自治体のルールに従って分別し、指定の場所に出せば回収してもらえます。しかし、オフィスや店舗など、事業活動によって生じたゴミは「事業系ごみ」に分類され、家庭ごみと一緒には捨てられません。
この事業系ごみは、さらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに大きく分けられます。
| 種類 | 説明 | 具体例 |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のもの。材質や成分によって厳しく規制されている。 | プラスチック類(椅子、OA機器の外装)、金属くず(スチールデスク、棚)、ガラスくず、コンクリートくず など |
| 事業系一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の事業系ごみ。 | 紙くず(書類、段ボール)、生ごみ(給湯室から出るもの)、木くず(木製家具)など |
ポイントは、多くのオフィス不用品が「産業廃棄物」に該当するという点です。そして、この産業廃棄物を収集・運搬するには、都道府県知事の「産業廃棄物収集運搬業許可」が必須となります。
会社のゴミは「産業廃棄物」。無許可業者への依頼は排出事業者(あなた)の責任に
もし、この許可を持たない無許可の業者に回収を依頼し、その業者が山中や空き地に不法投棄をした場合、どうなるでしょうか。
驚くべきことに、廃棄物処理法では「処理を委託した排出事業者(つまり、あなたの会社)にも責任がある」と定められています。たとえ知らなかったとしても、「委託基準違反」として罰金刑や懲役刑が科される可能性があるのです。
会社の信用を守るためにも、必ず許可を持つ正規の専門業者に依頼しなければならない、ということを最初に覚えておいてください。
品目別・廃棄物の分類一覧(デスク、PC、書類など)
オフィスでよく出る不用品が、どちらに分類されるのか具体例を見てみましょう。
| 品目 | 主な材質 | 廃棄物の分類 |
| スチールデスク、ロッカー、書庫 | 金属 | 産業廃棄物(金属くず) |
| オフィスチェア | 金属、プラスチック、布など | 産業廃棄物(金属くず、廃プラスチック類など) |
| パソコン、プリンター、複合機 | プラスチック、金属、ガラスなど | 産業廃棄物(金属くず、廃プラスチック類、ガラスくずなど) |
| パーテーション | アルミ、スチール、石膏ボードなど | 産業廃棄物(材質による) |
| 応接セット(ソファ、テーブル) | 木材、布、革、ガラスなど | 材質により産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれる |
| 書類、カタログ、段ボール | 紙 | 事業系一般廃棄物(紙くず)※ |
| 木製の机、椅子 | 木材 | 事業系一般廃棄物(木くず)※ |
※ただし、建設業など特定の業種から排出される紙くずや木くずは産業廃棄物扱いになるなど、例外もあります。実際には、ほとんどの専門業者が産業廃棄物と事業系一般廃棄物の両方の許可を持っているため、まとめて回収を依頼することが可能です。
1-2. 依頼する前に確認すべき社内準備リスト
業者へスムーズに見積もりを依頼し、社内の混乱を避けるために、事前に以下の3つの点を確認・準備しておきましょう。
処分品と残す物のリストアップ
まずは、何を処分し、何を残すのかを明確にします。エクセルなどで簡単な一覧表を作成し、「品目」「数量」「サイズ(大まかでOK)」「保管場所」などを記載しておくと、業者への情報伝達が非常にスムーズになります。可能であれば、処分対象物に付箋を貼るなどして、誰が見てもわかるようにしておくと、当日の作業が円滑に進みます。
リース物件か、購入品かの確認
特に注意したいのが「リース品」の扱いです。コピー機やビジネスフォン、一部のPCなどはリース契約になっていることがよくあります。これらは自社の資産ではないため、勝手に処分することはできません。
必ず資産台帳を確認したり、経理部門に問い合わせたりして、処分したいものが購入品かリース品かを確認してください。リース品の場合は、契約内容に従ってリース会社へ返却する必要があります。
情報システム部門・経理部門との連携
不用品処分は、総務部門だけで完結できないケースがほとんどです。
- 情報システム部門: PCやサーバー、ネットワーク機器を処分する場合、データ消去のルールや手続きについて必ず確認が必要です。情報漏洩を防ぐため、社内のセキュリティポリシーに従う必要があります。
- 経理部門: 処分する物品が、会社の資産として帳簿に計上されていないか(固定資産台帳の確認)を確認します。まだ資産価値が残っている場合は、廃棄損の会計処理(除却処理)が必要になるため、事前の連携が不可欠です。
これらの事前準備をしっかり行うことで、後のトラブルを防ぎ、業者とのやり取りから社内調整までをスムーズに進めることができます。
第2章:【最重要】失敗しない不用品回収業者の選び方と比較ポイント
ここが、オフィスの不用品処分を成功させる上で最も重要な章です。数多くの業者の中から、自社にとって最適なパートナーをどう見つけ出すか。料金の安さだけで判断するのではなく、企業の担当者として必ず確認すべき「3つの視点」から、業者選びのポイントを詳しく解説します。
2-1. 料金だけで選ぶのは危険!確認必須の2つの許可・資格
まず大前提として、事業系の不用品を回収するには国や自治体の許可が不可欠です。これらの許可がない業者は、そもそも比較検討の土台にすら上がりません。必ず公式サイトや見積書で以下の点を確認しましょう。
「産業廃棄物収集運搬業許可」は絶対条件
第1章で解説した通り、オフィスから出る不用品の多くは「産業廃棄物」です。これを収集・運搬するには、事業を行うエリアの都道府県知事から「産業廃棄物収集運搬業許可」を得ている必要があります。
【チェックポイント】
- 許可番号が明記されているか?
- 自社のオフィスの所在地が許可エリアに含まれているか?
- 許可証に記載されている「事業の範囲」に、処分したい品目(廃プラスチック類、金属くずなど)が含まれているか?
この許可は、適正な処理を行う業者であることの最低限の証明です。これが確認できない業者には、絶対に依頼してはいけません。
「古物商許可」(買取業務に必要)
もし、不用品の「買取」も希望しているなら、業者が「古物商許可」を各都道府県の公安委員会から得ているかを確認しましょう。中古品を買い取って販売するには、この許可が法律で義務付けられています。
この許可がある業者は、買取査定にも専門性を持っている可能性が高く、安心して取引ができる一つの目安となります。
2-2. サービス範囲で見極める「本当に頼れる」業者
買取対応力:オフィス家具・IT資産を専門的に査定できるか
買取は、コスト削減の最大のチャンスです。ここで重要なのは、オフィス用品の価値を正しく評価できる専門性があるかどうかです。
- 有名ブランドのオフィス家具やデザイナーズチェア
- 比較的新しいモデルのPCやサーバー、ネットワーク機器
- まだ使える複合機やプロジェクター
これらの価値を正しく査定できる専門スタッフがいる業者なら、高価買取が期待でき、処分費用を大幅に圧縮、場合によってはプラスになることさえあります。単に「何でも買い取ります」と言うだけでなく、オフィス什器やIT機器の買取実績が豊富な業者を選びましょう。
柔軟な対応力:夜間・土日祝の作業、急な追加依頼に対応できるか
「業務時間中の作業は困る」「退去日が迫っていて時間がない」といった悩みはつきものです。
- 業務時間外の作業(夜間、早朝、土日祝)に対応してくれるか
- 移転スケジュールに合わせた日時指定は可能か
- 「これも追加でお願いしたい」という急な依頼にも応じてくれるか
企業の事情を汲み取り、柔軟なスケジュールで対応してくれるフットワークの軽さも、信頼できるパートナーの重要な要素です。
2-3. 事前にチェック!企業の信頼性を見抜く方法

最後に、その企業がビジネスパートナーとして信頼に足るか、客観的な事実から判断しましょう。
豊富な法人対応実績と具体事例
家庭ごみの回収とオフィスの回収では、求められるノウハウが全く異なります。公式サイトなどで、法人向けのサービス案内が充実しているかを確認しましょう。。
📄 明確な料金体系と見積書
信頼できる業者は、料金体系が明確で、見積書の内訳も詳細です。
【良い見積書の例】
- 「作業費」「収集運搬費」「処分費」などの項目が分かれている
- 追加料金が発生する可能性のある作業(階段での搬出など)について、事前に説明がある
- マニフェストの発行費用など、諸経費についても記載がある
逆に、「一式 〇〇円」といった大雑把な見積書しか出さない業者は、作業後に追加料金を請求してくる可能性があり、注意が必要です。
🛡️ 損害賠償責任保険への加入の有無
プロの業者であっても、万が一の事故のリスクはゼロではありません。搬出作業中にビルの壁やエレベーターを傷つけてしまった場合に備え、「損害賠償責任保険」に加入しているかは必ず確認しましょう。
保険に加入していることは、リスク管理意識の高い、信頼できる企業であることの証です。見積もり時や問い合わせの際に、保険加入の有無とその補償内容について質問してみましょう。
第3章:気になる料金のすべて!費用相場とコスト削減の秘訣

不用品処分において、担当者の方が最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。この章では、料金がどのように決まるのか、具体的な相場はいくらなのか、そしてどうすればコストを賢く抑えられるのか、見積もりを取る前に知っておきたいお金の知識を徹底解説します。
3-1. 料金体系を徹底解説!「単品回収」と「トラック積み放題」
不用品回収の料金プランは、主に2つのタイプに分けられます。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合ったプランを選ぶことがコスト削減の第一歩です。
- 単品回収プラン 処分したいものが数点と少ない場合に適したプランです。「デスク1点につき〇〇円」「椅子1脚につき〇〇円」というように、アイテムごとに料金が設定されています。
- メリット:少量なら割安。料金が計算しやすい。
- デメリット:量が多くなると、合計金額が割高になる。
- トラック積み放題プラン 軽トラックや2tトラックなどの車両単位で料金が設定されており、規定の積載量までならどれだけ積んでも料金が変わらないプランです。オフィスの移転や閉鎖など、大量の不用品が出る場合に非常に有効です。
- メリット:大量の不用品をまとめて処分でき、1点あたりの単価が安くなる。
- デメリット:不用品の量が少ないと逆に割高になる。
品目別・料金相場一覧(単品回収の場合)
まずは、単品で依頼した場合のおおよその費用感を見てみましょう。
| 品目 | 費用相場(1点あたり) | 備考 |
| 事務机(スチール製) | ¥3,000 ~ | サイズや両袖・片袖などのタイプによる |
| オフィスチェア | ¥1,000 ~ | 機能や素材による |
| パソコン(デスクトップ/ノート) | ¥1,000 ~ | データ消去費用が別途かかる場合が多い |
| 業務用コピー機・複合機 | ¥10,000 ~ | 重量物扱いで作業員が複数名必要 |
| スチール書庫・ロッカー | ¥4,000 ~ | サイズや扉の数による |
| 会議用テーブル | ¥3,000 ~ | サイズや材質による |
| パーテーション | ¥2,000 ~ | 1枚あたりの価格。解体費が別途の場合も |
※上記はあくまで目安です。業者や地域、搬出状況によって料金は変動します。
トラック積み放題プランの料金相場
次に、まとまった量がある場合に有効な積み放題プランの相場です。
| トラックのサイズ | 費用相場 | 積載量の目安 |
| 軽トラック | ¥15,000 ~ | 事務机2台+椅子4脚+PC類など |
| 2tトラック | ¥50,000 ~ | 10名前後の小規模オフィスの什器一式など |
自社に合ったプランの選び方
- 処分したいものが5点以下の場合 → 「単品回収」 が割安になる可能性が高いです。
- デスクや椅子がそれぞれ5点以上ある、フロアの一部を整理したい場合 → 「トラック積み放題」 の方がお得になるケースがほとんどです。
最終的には、見積もり時に業者に「単品で計算した場合と、積み放題プランの場合、どちらが安くなりますか?」と直接質問するのが最も確実です。
3-2. 見積もりで必ずチェックすべき5つの項目
業者から見積書を受け取ったら、合計金額だけを見るのではなく、その内訳をしっかり確認する癖をつけましょう。不明瞭な点があると、後々のトラブルの原因になります。
1. 基本料金、出張費、人件費の内訳
「作業一式」とまとめられていませんか?「基本料金」「出張費」「作業員〇名分」といったように、費用の内訳がきちんと記載されているかを確認しましょう。
2. 追加料金が発生するケース
以下の作業は、基本料金に含まれず「”後出し”の追加料金」として請求され、トラブルになりやすい項目です。自社のオフィス環境と照らし合わせ、見積もり時に「この作業は発生しそうですか?その場合、費用はいくらですか?」と事前に必ず確認しておきましょう。
① 階段料金:エレベーターが使えない環境での搬出
エレベーターが使えない、またはエレベーターに入らない大型の什器を運び出す際に発生します。
- どのような場合に発生するか?
- そもそもエレベーターがないビル(特に築年数の古い雑居ビルなど)。
- 大型のL字デスクや会議テーブルなどが、エレベーターの扉や内部の広さの問題で入らない。
- ビルの規約で、引越しや搬出作業でのエレベーター使用が禁止されている、または時間が厳しく制限されている。
- 料金の目安と決まり方
- 「作業員1名につき、1フロアごとに1,000円~3,000円」が一般的な相場です。
- 例えば、「作業員2名で3階から搬出」する場合、「2名 × 2フロア分(3階→1階) × 2,000円 = 8,000円」のような計算になります。
- 業者によっては、フロアごとの一律料金を設定している場合もあります。
- 担当者のチェックポイント 見積もり時に「見積もり料金はエレベーター作業が前提ですか?」「もし階段を使う場合、料金体系はどうなりますか?」と明確に質問しましょう。
② 解体作業費:そのままでは運び出せない什器の分解
大型の家具やパーテーションは、そのままでは部屋のドアや廊下、エレベーターを通らないため、一度分解してから運び出す必要があります。その分解作業にかかる手間賃が解体作業費です。
- どのような場合に発生するか?
- 役員用の大型デスク、L字デスク、連結式のシステムデスク。
- 大型の会議テーブルや応接テーブル。
- オフィスを間仕切りしているパーテーションの撤去。
- 壁際に作り付けられた収納棚やカウンター。
- 料金の目安と決まり方
- デスク1台あたり:3,000円~8,000円
- パーテーション1枚あたり:2,000円~6,000円
- 料金は、ネジを外すだけの簡単なものか、複雑な構造かといった「解体の難易度」や「所要時間」によって変動します。
- 担当者のチェックポイント 業者による現地見積もりの際に、「このデスクは解体が必要ですか?」「パーテーションの解体・撤去もお願いしたいのですが、費用は見積もりに含まれていますか?」と、対象物を指し示しながら確認するのが最も確実です。
③ 重量物作業費:特殊な機材や追加の人員が必要な搬出
この費用は、単に「重いから」という理由だけで発生するのではありません。安全な搬出のために必要な「専門技術」「追加人員」「専用機材」に対する対価であり、御社のオフィスと従業員、そして作業員自身を守るための重要なコストです。
なぜ、追加料金がかかるのか? その内訳
人の手だけでは安全に運べない「重くて大きいもの」の搬出には、以下のような通常業務とは異なる要素が含まれます。
- 専門的なスキルと経験: 重量物の搬出は、単なる力仕事ではありません。重心の取り方、テコの原理の応用、角を曲がる際の連携など、熟練したチームワークと経験がなければ、壁や床を傷つけたり、最悪の場合は人身事故につながったりします。
- 追加人員の確保: 安全基準上、例えば100kgを超えるような複合機は、通常の2名体制ではなく、3~4名以上の人員で対応するのが一般的です。この追加の人件費が直接料金に反映されます。
- 専用機材と養生(ようじょう): 重量物専用の台車(パワーリフター機能付きなど)、運搬用のベルト、そして最も重要なのが、搬出経路の床や壁、エレベーター内を保護するための**「養生」**です。専用のパネルやシートで徹底的に保護することで、万が一の物損事故を防ぎます。この資材費と設置の手間も費用に含まれます。
【具体例】品目別の料金目安と変動要因
料金は「基本料金+オプション」で構成され、搬出経路の難易度によって大きく変動します。
| 品目・重量の目安 | 料金の目安 | 特に価格を左右する要因(チェックポイント) |
| 中型コピー機・複合機 (約80kg~120kg) | ¥15,000 ~ | ・階段作業の有無(1フロアごとに+¥5,000~が目安) ・搬出経路に狭い場所や段差はないか ・作業員の必要人数(3名か4名か) |
| 大型コピー機・複合機 (約120kg~200kg) ※印刷会社や設計事務所など | ¥30,000 ~ | ・カウンターや壁際にピッタリ設置されていないか(引き出すスペースが必要) ・搬出のためにドアや一部の什器を外す必要はないか |
| オフィス用耐火金庫 (約100kg~150kg) | ¥25,000 ~ | ・床にボルトで固定されていないか(固定解除の作業費が別途発生) ・階段作業の場合、料金が大幅に上がる傾向がある |
| サーバーラック(中身あり) (約150kg以上) | ¥40,000 ~ | ・IT専門の作業員が必要か ・サーバーや機器の取り外し(ラッキング解除)は誰が行うか ・データ消去などの付随サービスも依頼するか |
※上記はあくまでエレベーターが利用できる場合の一般的な目安です。
【担当者のアクション】見積もりで失敗しないためのチェックポイント
当日になって「聞いていない」という事態を避けるため、以下の準備と質問を徹底しましょう。
《準備すること》
- 型番(品番)を調べる: 複合機や金庫の側面・背面に貼られているシールで型番を確認し、インターネットで検索すれば、正確な「重量」と「寸法(幅・奥行・高さ)」がわかります。この情報を業者に伝えるだけで、見積もりの精度が格段に上がります。
- 搬出経路の写真を撮る: 対象物が設置されている場所から、部屋のドア、廊下、エレベーター、建物の出口までの道のりをスマートフォンで撮影しておきましょう。特に「狭い曲がり角」「通路の段差」などは重要です。
《見積もり時に質問すること》
- 「〇〇社製の△△(型番)という複合機で、重さは約120kgです。この情報で見積もりをお願いします」
- 「作業員は何名体制になりますか? その人件費は見積もりに含まれていますか?」
- 「床や壁の養生は、どの範囲までやっていただけますか? 養生費用は別途かかりますか?」
- (階段の場合)「階段を使った場合の追加料金は、1フロアあたりいくらですか?」
このように、事前に具体的な情報をこちらから提供し、専門的な質問を投げかけることで、業者は正確な見積もりを出さざるを得なくなります。これにより、不当な追加請求のリスクを限りなくゼロに近づけることができるのです。
3. 車両費、駐車料金の有無
トラックの費用(車両費)が基本料金に含まれているかを確認します。また、オフィスの前にトラックを停めるスペースがない場合、近隣のコインパーキング代が実費で請求されることがほとんどです。この点も見落とさずに確認しましょう。
4. マニフェスト(管理票)の発行費用
適正処理を証明する重要な書類である「マニフェスト」は、発行に数百円程度の手数料がかかるのが一般的です。見積もりに記載があるか、もしくは発行してもらえるかを確認してください。
3-3.【実践テクニック】処分費用を賢く抑える3つの方法
最後に、担当者としてぜひ実践していただきたいコスト削減のテクニックをご紹介します。
テクニック1:「買取」を最大限に活用し、費用と相殺する
最も効果的なコスト削減策が、不用品を「ゴミ」ではなく「資産」として買い取ってもらうことです。
- 価値のあるもの:購入から5年以内の新しいPC、有名メーカーのオフィスチェア、状態の良いスチール家具など
- 衣頼方法:見積もり時に「買い取れるものはありませんか?」と必ず尋ね、処分費用から買取金額を差し引いてもらうよう交渉しましょう。
これにより、処分費用が大幅に安くなるだけでなく、買取金額が上回ってプラスになるケースさえあります。
テクニック2:可能な範囲で自社で分別・整理しておく
業者の作業時間を少しでも短縮できれば、人件費の削減につながる可能性があります。すべてを「丸投げ」するのではなく、以下のような簡単な準備をしておくだけでも効果的です。
- 処分品を1ヶ所にまとめておく
- PCの電源コードやマウスなどを外して袋にまとめておく
- 書類や細かいゴミなどを事前に分別し、段ボールに入れておく
これらのひと手間が、結果的に数千円〜数万円のコスト削減に繋がることもあります。
第4章:依頼から完了まで!事務所の不用品回収の具体的な流れと各ステップの注意点

信頼できる業者を見つけたら、いよいよ具体的な手続きに進みます。ここでは、問い合わせから作業完了までの一連の流れを5つのステップに分けて解説します。各ステップでの注意点を押さえておくことで、トラブルなくスムーズにプロジェクトを進行させることができます。
STEP1:問い合わせ・相談
まずは、候補となる業者に電話やウェブサイトの問い合わせフォームから連絡を取ります。
- 伝えるべき基本情報
- 会社名、担当者名、連絡先
- オフィスの所在地(ビル名、階数)
- 不用品のおおよその内容と量(例:「事務机10台、椅子20脚ほど」)
- 希望する作業日時
- エレベーターの有無や、搬出経路に関する特記事項
- この段階での注意点 この時点では、まだ詳細な見積もりは出せません。電話やメールだけで「総額〇〇円です」と確定金額を提示してくる業者は、後から追加料金を請求してくる可能性があるため、むしろ注意が必要です。この段階では、「現地見積もりの日程調整」をゴールと考えましょう。
STEP2:現地調査・見積もり
業者の担当者がオフィスに来訪し、処分する不用品の量や種類、搬出経路などを直接確認します。この現地調査が、正確な見積もりを出すための最も重要なプロセスです。
- 担当者が立ち会う際のポイント
- 処分するものを正確に伝える: STEP1で準備したリストを元に、どれが処分対象で、どれを残すのかを明確に指し示します。
- 懸念事項をすべて質問する: 「この大型金庫も大丈夫ですか?」「パーテーションの解体もお願いできますか?」など、少しでも不安な点はすべて質問し、見積もりに含めてもらうように依頼します。
- 買取希望の品を伝える: 「この椅子は新しいので、買い取れませんか?」など、価値がありそうなものは積極的にアピールしましょう。
- この段階での注意点 原則として、法人対応に慣れている業者であれば、現地調査と見積もりは無料です。 もしこの段階で出張費や見積もり作成費を請求する業者がいれば、その業者への依頼は見送るのが賢明です。見積書は、可能であればその場でもらうか、遅くとも2〜3日以内にメールなどで送付してもらいましょう。
STEP3:搬出・回収作業当日
契約内容に基づき、業者がオフィスへ来て搬出・回収作業を行います。
- 当日の担当者の役割
- 作業開始前の最終確認: 作業範囲(どれを処分するか)について、業者スタッフと改めて指差し確認を行います。
- 作業の立ち会い: 基本的には業者がすべて行いますが、何か不明点や判断に迷うことが発生した場合に備え、責任者として立ち会います。共有スペースや他のテナントに迷惑がかかっていないかなども、軽く気配りできるとよりスムーズです。
- 作業完了後の確認: すべての不用品が回収されたか、搬出経路に傷などがついていないかを作業責任者と一緒に確認します。
- この段階での注意点 ビル管理会社によっては、作業前に「作業届」の提出や、エレベーターや共用廊下の「養生(保護)」に関する細かいルールが定められている場合があります。業者と事前に打ち合わせを行い、ビルの規約を遵守するように依頼しておきましょう。
STEP4:支払い・各種証明書の受領
作業が完了したら、契約に基づき料金を支払います。法人取引の場合、多くは後日請求書払いとなります。
第5章:【ケース別】こんな時はどうする?よくあるお悩み解決Q&A

これまでの章でオフィス不用品処分の基本を解説してきましたが、実際の現場では様々な状況が考えられます。この章では、特にご相談の多い3つのケースと、担当者の方が抱えがちな2つの疑問について、具体的な解決策をQ&A形式でご紹介します。
ケース1:オフィスの「移転・縮小」に伴う大量処分
【お悩み】
「来月末の移転までに、今のオフィスを完全に空にする必要があります。新しいオフィスに持っていくもの、捨てるもの、売れるものが混在しており、何から手をつければいいかわかりません。とにかく時間がないのが一番の悩みです。」
【解決策】
オフィスの移転・縮小で最も重要なのは「スケジュールの管理」と「作業の効率化」です。
- 最低でも2ヶ月前から準備を開始する 移転日が決まったら、すぐに不用品回収業者の選定を始めましょう。特に年度末の3月や年末の12月は業者の繁忙期にあたるため、早めに予約しないと希望の日時が押さえられない可能性があります。
- 「移動」「買取」「処分」の3つに仕分ける 業者に見積もりを依頼する前に、社内で不用品を以下の3種類に分類しておきましょう。
- 【移動】→ 新オフィスへ持っていくもの
- 【買取】→ 価値がありそうで、売却したいもの
- 【処分】→ 上記以外の廃棄するもの
- この仕分けを元に見積もりを取ることで、引越し費用と処分費用、そして買取金額が明確になり、トータルコストを正確に把握できます。
ケース2:会社の「閉鎖・倒産」による全資産の処分
【お悩み】
「会社の事業終了に伴い、事務所内にあるすべての物品を現金化、もしくは処分する必要があります。法的な手続きも絡むため、資産価値を正しく評価し、適切に処理してくれる信頼できるパートナーが必要です。」
【解決策】
このケースでは、単なる不用品処分ではなく「資産の現金化(リクイデーション)」という視点が最重要になります。
- オフィス資産の「一括査定・買取」に強い業者を選ぶ
通常の不用品回収業者よりも、法人資産の買取や倒産案件の整理に特化した専門業者への相談が有効です. これらの業者は、オフィス家具やPCだけでなく、専門機器や在庫品まで含めたオフィス内の全資産をまとめて査定し、「現状有姿(げんじょうゆうし)での一括買取」を提案してくれることがあります。これにより、迅速な現金化と事務所の明け渡しが可能になります。
- 弁護士や破産管財人との連携実績を確認する
事業の閉鎖には、弁護士などの法律専門家が関与することがほとんどです。業者を選ぶ際には、過去に弁護士や破産管財人と連携して管財物件の処理を行った実績があるかを確認しましょう。法的手続きを理解している業者であれば、必要書類の作成などもスムーズに進みます。
- 機密情報の抹消は絶対条件
会社の最後の信頼を守るため、顧客情報や財務情報などの機密データは、どんなに小さなものでも確実に抹消しなければなりません。データ消去や書類溶解の証明書発行が、絶対条件であることを念頭に置いて業者を選定してください。
ケース3:「レイアウト変更」で出た少量の不用品
【お悩み】
「部署のレイアウト変更で、事務机が3台と椅子が5脚、古い書庫が1台不要になりました。量は少ないのですが、どう処分するのが最も効率的でコストを抑えられますか?」
【解決策】
少量であっても、事業活動から出たゴミは産業廃棄物です。安易に「無料回収」などを利用せず、正規のルートで処分することが大前提です。
- 「単品回収」と「軽トラック積み放題」を比較検討する 第3章で解説した通り、料金プランを比較しましょう。業者に見積もりを依頼する際に、「単品で計算した場合」と「軽トラックプランを使った場合」の両方の金額を提示してもらい、安い方を選ぶのが賢い方法です。
- 地域密着型の業者も視野に入れる 全国展開の大手だけでなく、自社のオフィスがある地域(例:大阪市中央区など)に根ざした地域密着型の業者は、出張費が安く、フットワーク軽く対応してくれることがあります。少量の案件であれば、こうした業者の方がコストパフォーマンスに優れている場合も少なくありません。
- 急ぎでなければ「保管」も選択肢 もし保管スペースに余裕があるなら、すぐに処分せず、次回のまとまった不用品が出るタイミングまで保管しておくという手もあります。量をまとめることで、トラック積み放題プランなどを利用し、1点あたりの処分単価を下げることができます。
よくあるお悩みQ&A
Q. リース品が混ざっている場合は?
A. 絶対に処分してはいけません。リース会社への返却が必要です。
リース品は、あくまでリース会社から借りている「資産」であり、自社の所有物ではありません。誤って処分・売却してしまうと、契約違反となり損害賠償を請求される可能性があります。
【対応手順】
- 特定する: 経理部門に資産台帳を確認してもらうか、機器に貼られている管理シール(「〇〇リース」など)でリース品かどうかを特定します。
- 分離する: 処分品とはっきりと区別できる場所に移動させ、「リース品:返却予定」などの張り紙をして、誤って回収されないようにします。
- 契約に従い返却する: リース会社に連絡を取り、契約書に定められた手続きに従って返却します。業者によっては、この「返却代行」を請け負ってくれる場合もあります。
Q. ビルの管理会社への届け出は誰がやる?
A. 届け出の「責任」はテナント(自社)にありますが、実務は業者が代行するのが一般的です。
ビルとの賃貸借契約を結んでいるのはあくまで自社ですので、搬出作業を行う旨をビル管理会社へ連絡する一次的な責任は、テナント側にあります。
しかし、プロの不用品回収業者であれば、その後の実務的な手続きは全て代行してくれます。
【一般的な流れ】
- テナント(あなた): まずビル管理会社に「〇月〇日に不用品の搬出作業を予定している」と第一報を入れ、担当者の連絡先を入手します。
- テナント(あなた): 決定した不用品回収業者に、ビル管理会社の担当者連絡先を伝えます。
- 不用品回収業者: ビル管理会社と直接連絡を取り、以下の調整を行います。
- 作業届などの必要書類の提出
- エレベーターや共用廊下の養生(保護)方法の確認
- 搬出作業を行う時間帯(特にサービス用エレベーターが使える時間)の調整
「ビル管理会社との調整も、当方で代行しますのでご安心ください」と積極的に言ってくれる業者は、法人対応に慣れている信頼できるパートナーだと判断して良いでしょう。
はい、承知いたしました。ガイド全体の締めくくりとなる「おわりに」を執筆します。
おわりに:信頼できるパートナーを見つけ、スムーズなオフィス環境の再構築を
ここまで、オフィスの不用品処分・回収に関する全てのプロセスを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
改めてお伝えしたいのは、会社の不用品処分は単なる「片付け」ではなく、コスト管理、コンプライアンス、情報セキュリティ、そして時間管理といった、企業の根幹に関わる要素が詰まった重要な「事業活動」であるということです。
一見、面倒で複雑に感じるかもしれませんが、信頼できる専門業者を「パートナー」として見つけることができれば、その負担の大部分を軽減することが可能です。良いパートナーは、あなたの会社の状況を深く理解し、法律やルールを遵守しながら、最も効率的でコストメリットのある方法を提案してくれます。
古い什器や不要な書類がなくなったクリーンなオフィスは、従業員の生産性を高め、新しいビジネスを生み出すための土台となります。このガイドが、あなたの会社のスムーズなオフィス環境の再構築の一助となれば幸いです。
最重要ポイントのまとめ
最後に、これだけは絶対に忘れないでほしいという最重要ポイントをチェックリストとしてまとめました。業者へ相談する前に、ぜひ一度見返してみてください。
- □ 法的責任の所在を理解する オフィスから出るゴミ(産業廃棄物)の処理責任は、最終的に排出事業者である「自社」にある。
- □「産業廃棄物収集運搬業許可」を必ず確認する この許可がない業者は、比較検討の対象外。会社の信頼を守るための絶対条件。
- □ コストは「買取」で最適化する 複数社を比較し、価値のあるものは買い取ってもらうことで、処分費用は大幅に削減できる。
- □ 契約は必ず「書面」で交わす 口約束はトラブルの元。産業廃棄物処理委託契約書を必ず締結する。
まずは気軽に複数の業者へ相談してみよう
多くの情報を一度にインプットし、少し圧倒されているかもしれません。しかし、次に行うべきアクションは非常にシンプルです。
まずは、気になった業者「相談」という形で気軽に連絡を取ってみましょう。
法人対応に優れた業者であれば、あなたの漠然とした悩みや疑問に対しても、親身にアドバイスをくれるはずです。そして、ほとんどの場合、現地での状況確認や見積もりの作成は無料です。
このガイドで得た知識を武器に、ぜひ専門家である業者へ具体的な質問をぶつけてみてください。その対応力や提案力を見比べることで、自社にとって本当に信頼できるパートナーがきっと見つかるはずです。
あなたの会社のオフィス整理プロジェクトが、成功裏に完了することを心から願っています。