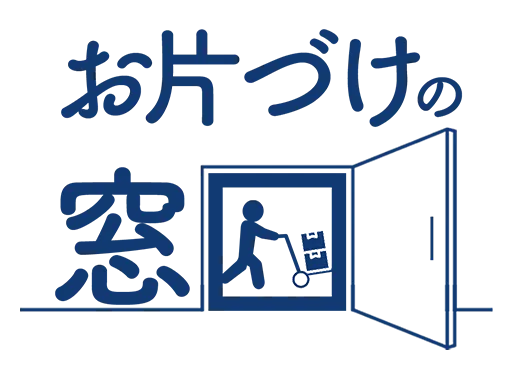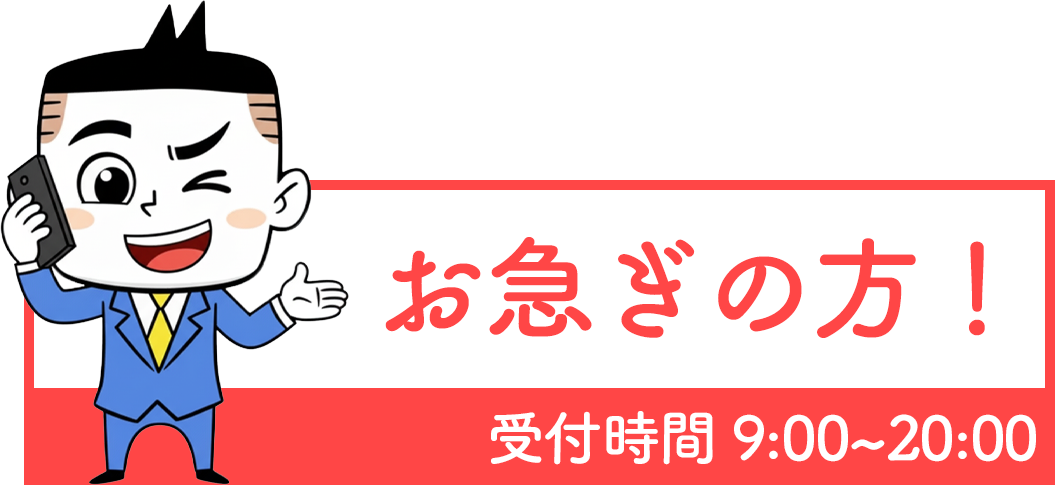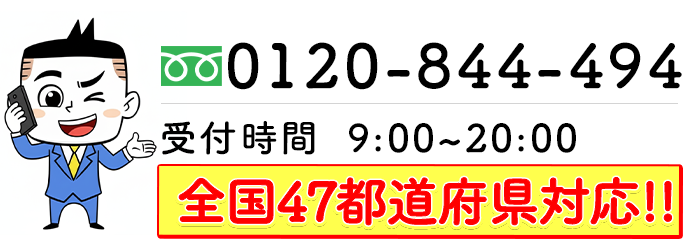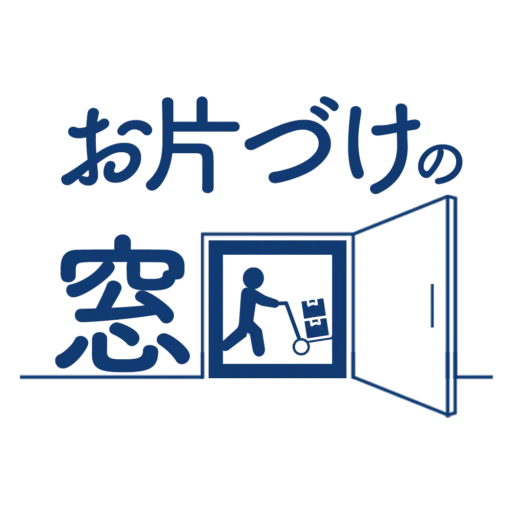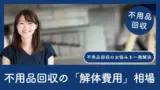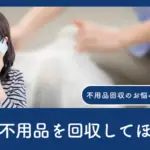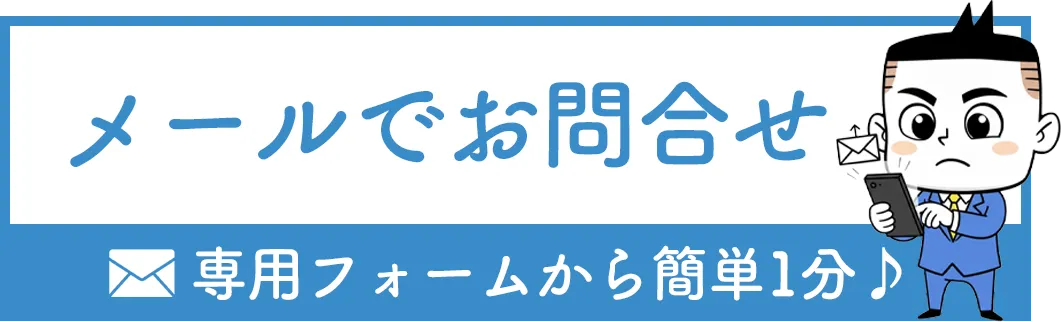編集長
私自身、過去に何度も不用品回収サービスに助けられた
元・ヘビーユーザーです。
その実体験から、いざという時に頼れる『利用者目線の情報』をお届けするという
理念を掲げ、実体験に基づいた情報をお届けします!
第1章:「2トントラック積み放題」の料金と量のウソ・ホント
「2トントラック積み放題、5万円!」
ネットやチラシでこんな広告を見ると、たくさんの不用品に困っている時には「これなら全部片付くかも」と、つい期待してしまいますよね。
でも同時に、「本当にこの金額で全部やってくれるのかな?」「何か裏があるんじゃないか…」と、少し不安になる気持ち、ありませんか?
実は私も以前に実家の片付けで、まさにその不安が現実になりかけた経験があるんです。
1-1. まずは基本!「積み放題」のルールと限界ライン
数年前、父が亡くなり、残された実家を片付けなければならなくなった時のことです。2部屋分が、父の趣味の道具や古い家具、たくさんの本で埋まっていて、どこから手をつけていいか分からない状態でした。
そこで見つけたのが、「積み放題」を安くうたう業者さん。「この量なら全然大丈夫ですよ」という電話の言葉を信じて、お願いすることにしたんです。これが、最初の失敗でした。
1-1-1. どこまでが「積み放題」?荷台の高さと「カゴ台車」の罠
当日来てくれたトラックを見て、まず最初に「あれ?」と思いました。荷台の周りにある囲いが、思っていたよりもずっと低かったんです。
そう、「積み放題」と言っても、無制限に積めるわけではありません。ほとんどの場合、トラックの荷台の囲い(専門用語では「アオリ」と言うそうです)の高さを超えない範囲まで、というのが基本的なルールです。
私が「これ、全部乗りますかね…?」と心配そうに聞くと、作業員の方はにこやかにこう言いました。
「もし乗り切らなくても、こちらの『カゴ台車』を使えば大丈夫ですよ。1台追加で1万5千円になりますけどね」
それを聞いて、正直「えっ」と思いました。カゴ台車というのは、スーパーなどでも見かける、キャスター付きの大きなカゴのことです。不用品回収では、トラックに乗らなかった分をこのカゴ台車で測って、「カゴ1台分」として追加料金を取る、というやり方があるんですね。
つまり、基本料金を安く見せておいて、当日「乗り切らない」という状況を作ってから、このカゴ台車で追加料金を請求する、というケースがあるんです。私が頼んだ業者がまさにそうだったのかは分かりませんが、そう思われても仕方がないやり方だな、と感じました。
まず大事なのは、「積み放題」は無限ではない、ということ。「荷台の囲いの高さまで」という、はっきりした上限があることを知っておくのが大切です。
1-1-2. 優良業者は知っている「上手な積み方」と「下手な積み方」
結局、私はその業者さんにはお断りして、後日、きちんと説明してくれた別の業者さんにお願いし直しました。そして、その時の作業を見て、本当に驚きました。
新しい業者さんは、まず不用品全体を眺めて、どれから積むか考えているようでした。
- 下手な積み方
- 大きな家具から適当にトラックに乗せて、空いた場所に小物を詰めるやり方です。これだと、家具と家具の間にどうしても無駄な隙間ができてしまいます。結果的にすぐ荷台がいっぱいになり、「もう積めません」となってしまいがちです。
- 上手な積み方(私が見たプロのやり方)
- まず、本や食器のように重くて形が四角いものを下に敷き詰めて、土台を作ります。
- 次に、解体できる棚などはちゃんとバラして、板の状態で隙間に差し込んでいきます。
- そして、家具と家具の間にできた変な形の隙間には、布団やクッションといった柔らかいものをクッション代わりのように詰めていくんです。
本当にパズルのようで、あれだけたくさんあった不用品が、どんどん荷台に収まっていきました。結局、カゴ台車なんて全く使うことなく、すべての片付けが終わりました。
この経験で分かったのは、同じ2トントラック1台でも、業者さんの技術や経験によって、実際に積める量は全く違ってくる、ということです。
料金の安さも大事ですが、それ以上に「どういう風に作業してくれるのか」という点も、業者さんを選ぶときには見たほうがいい、と心から思いました。
1-2. 我が家の荷物は本当に全部乗る? 具体的な物量で考えてみましょう

「積み方で量は変わる」と分かっても、やっぱり一番知りたいのは「で、うちの荷物の場合、どうなの?」ということですよね。
業者さんがよく言う「ワンルーム分」という目安は、あってないようなもの。人によって物の量は全然違いますから。ここでは、もっと具体的に、家具や家電の種類ごとに「これくらい積んだら、荷台はこれくらい埋まる」という感覚を掴んでいきましょう。
1-2-1. 《家具編》ダブルベッド・大型ソファ・食器棚…大きいものは何個まで?
まず、トラックのスペースを一番占領するのが、ソファやタンスといった大きな家具です。これらがいくつあるかで、残りのスペースがだいたい決まります。
一つの簡単な目安として、下のリストにあるような大きな家具が「3つか4つ」あると、2トントラックの荷台はかなり埋まってしまうと思ってください。
【スペースを大きく取る家具の例】
- ダブルベッド(マットレスと解体したフレーム)
- 2~3人掛けのソファ
- 大きめの食器棚や本棚
- 洋服ダンス
- 4人掛けのダイニングテーブルセット
例えば、「ダブルベッド」「3人掛けソファ」「洋服ダンス」を積んだら、残りの空間にはテレビ台や衣装ケース、段ボールが少し入る程度です。もし、ご自宅にこれらリストの家具が5つも6つもある場合は、2トントラック1台では厳しいかもしれません。
ここで大事なのが、「解体できるかどうか」です。私の父の家では、大きな洋服ダンスはありましたが、幸いベッドが解体できるパイプベッドだったので助かりました。もしこれが、解体できない作りの立派なベッドだったら、他の何かを諦める必要があったと思います。形を変えられないソファなどは、特に場所を取る、と考えておくと間違いありません。
1-2-2. 《家電編》4ドア冷蔵庫やドラム式洗濯機、リサイクル料金以外の注意点
冷蔵庫や洗濯機のような大きな家電も、もちろん積んでもらえます。
ただ、これらも家具と同じくらい場所を取ります。特に、最近の大きな冷蔵庫やドラム式洗濯機は、昔のものより奥行きがあるので、思った以上にかさばります。
スペースの話とは少しずれますが、一点だけ。家電の扱いに慣れている業者さんかどうかも、見ておくと安心です。例えば、冷蔵庫はすぐに電源を切ると故障の原因になることがあるので、「前日の夜にはコンセントを抜いておいてくださいね」と事前に教えてくれるような業者は、経験が豊富で親切だな、と感じます。
1-2-3. 《“かさばる物”編》布団・衣装ケース・カーペットの賢いまとめ方
次に、布団や衣類、カーペットのように「軽いけどかさばる物」たちです。これらは、まとめ方次第で占領するスペースが大きく変わります。
私の母は来客用の布団をたくさん持っていたのですが、これが片付けの時に本当に場所を取って…。その時、上手な業者さんは、布団をただ積むのではなく、圧縮袋に入れたり、ロープやヒモでぎゅっと縛って、できるだけ小さくしてから積んでくれました。
もしご自身で少しでも準備できるなら、
- 布団や毛布:ヒモで縛るか、大きなビニール袋に入れて空気を抜いておく
- 洋服:衣装ケースや段ボールに詰める(袋に入れると積みにくい)
- カーペット:丸めてヒモで縛っておく
これだけで、トラックのスペースを有効に使えますし、作業もスムーズに進みますよ。
1-2-4. 《“重い物”編》本・雑誌・食器類、重さで断られない?

「うち、本がすごく多いんだけど、重すぎて断られたりしない?」 これも、実際に私が心配したことでした。父が本好きで、壁一面が本棚だったんです。
結論から言うと、一般的な家庭の片付けで、重さが原因でトラックに乗せられない、ということはまずありません。 2トントラックは、重さにして2,000kg(2トン)まで積める法律になっています。本や食器だけで2トンを超えるというのは、よっぽどでない限り考えにくいです。
ただし、注意点が一つだけ。それは「箱詰めの仕方」です。
私もやりかけたのですが、一番大きな段ボールに本をぎっしり詰めてしまうと、大人の男性でも持ち上げられないくらい重くなってしまいます。無理に運ぼうとすると、段ボールの底が抜けたり、作業員さんが腰を痛めたりする原因にもなりかねません。
本や食器のように重いものは、「小さい段ボールに小分けに入れる」のが鉄則です。業者さんからも「その方が運びやすいですし、トラックの中でも重さを分散して積めるので助かります」と言われました。もしご自身で箱詰めされる場合は、この点を気をつけてみてください。
1-3. 最悪の事態!「トラックに乗りません…」その時どうなる?
ここまで、トラックにどれくらい荷物が乗るのかを考えてきましたが、どれだけ慎重に計算しても、当日になって「あと少しだけ乗らない…」という事態は、残念ながら起こり得ます。
不用品が目の前に残って、トラックは帰ってしまう。考えただけでも、頭が真っ白になりますよね。でも、大丈夫。もしそうなってしまっても、慌てずに対処する方法はちゃんとあります。大事なのは、そうなった時にどんな選択肢があって、それぞれいくら位かかるのかを、事前に知っておくことです。
1-3-1. 超過分の料金体系をチェック!「1点追加〇円」と「ミニカゴ追加〇円」の相場
もしトラックの容量を超えてしまった場合、業者さんが提案してくる追加料金のプランは、だいたい2種類です。
- ① 1点ずつ追加していくパターン 残った不用品を指さして、「これは追加で〇円、これも〇円」というふうに、1つずつ料金が決まるやり方です。少量のオーバーなら、こちらのほうがお得なことが多いです。 料金の目安としては、 ・ゴミ袋1つ、小さなイスなど:500円~2,000円くらい ・電子レンジ、衣装ケースなど:2,000円~4,000円くらい ・小さめの棚など:4,000円~6,000円くらい が相場のようです。ただ、これは業者さんによって本当にバラバラなので、必ずその場で確認してください。
- ② 「カゴ台車」で追加するパターン 前の章で少し触れた、あの銀色のカゴを使う方法です。「カゴ1台に積めるだけ積んで、追加〇円」という料金設定です。 料金の相場は8,000円~15,000円くらいと、結構高めです。残った荷物が段ボール数箱分など、ある程度まとまった量がある場合はこちらを提案されることが多いかもしれません。
どちらのパターンになるかは、業者さんの方針と、残った荷物の量次第です。一番大事なのは、最初の見積もりを取る段階で、「もし乗り切らなかったら、追加料金はどうなりますか?」と、はっきり聞いておくこと。 これを聞くだけで、悪質な業者さんはごまかせなくなるので、自分を守るためにも必ず質問しておきましょう。
1-3-2. 「少しだけオーバー」なら交渉できる?言ってみる価値アリのひと言
もし、残ってしまったのが本当に「あと、この小さい棚だけ」「段ボール一箱だけ」といった、ごく少量だった場合。ダメ元で、少しだけ交渉してみる価値はあります。
もちろん、無理な値引き交渉は禁物です。一生懸命作業してくれた方に失礼ですし、関係も悪くなってしまいます。そうではなくて、あくまで「お願い」ベースで、丁寧に伝えてみるのがコツです。
私の実家の片付けの時も、実は最後に小さな脇息(わきそく。肘置きみたいなものです)が一つだけ残ってしまったんです。その時、私が作業の責任者の方に、
「すみません、私の計算ミスで…。あとこれだけなんですけど、どうにか隙間に乗せてもらえたりはしませんか…?」
と、申し訳ない気持ちで伝えてみました。すると責任者の方は、少し荷台の中を整理してくれて、「ここなら入りますよ」と、サービスで積んでくれたんです。
もちろん、いつでも上手くいくとは限りません。でも、「こちらの計算ミスであること」をきちんと認めた上で、丁寧にお願いしてみる。 これだけで、相手の心証は全く変わってきます。言ってみるだけなら損はありませんから、もしもの時は試してみてください。
1-3-3. もう一台追加?諦めて粗大ごみ?賢い選択肢とは
交渉も難しく、残った荷物も結構な量がある。そんな時は、冷静に判断しなければなりません。選択肢は大きく3つです。
- 選択肢①:業者の追加料金を払って、全部持っていってもらう 一番楽な方法です。費用はかかりますが、「今日この場ですべてを終わらせたい」という場合は、この選択が良いでしょう。
- 選択肢②:残ったものを諦めて、自分で処分する 一番安く済む方法です。残ったものが、お住まいの自治体の「粗大ごみ」で出せるものなら、数百円~千円ちょっとで処分できます。ただし、自分で指定の場所まで運んだり、収集日まで待ったりする手間はかかります。
- 選択肢③:日を改めて、別の業者を探す(または同じ業者にもう一度頼む) 残った荷物が多すぎて、追加料金が高額(数万円)になる場合は、この選択も考えられます。ですが、また見積もりからやり直しになるので、一番手間と時間がかかります。
私のおすすめは、あらかじめ「諦めてもいい物リスト」を頭の中で作っておくことです。
「このタンスとソファだけは絶対に今日持っていってほしいけど、最悪、このカラーボックスと古本は、後で自分で粗大ごみに出してもいいかな」というように、優先順位をつけておくのです。
そうすれば、万が一「全部は乗りません」と言われた時も、慌てずに「では、このカラーボックスと本は大丈夫です」と、その場でスムーズに判断できます。心の準備をしておくだけで、当日の安心感が全く違いますよ。
1-4. 大量の不用品回収だからこそ要注意!基本料金に隠された「追加料金」リスト
「2トントラック積み放題、5万円!」という広告の金額。これが、当日支払う「すべての金額」だと思っていると、会計の時にびっくりすることがあります。
特に、私たちのようたくさんの不用品をまとめてお願いする場合、家や荷物の状況によっては、どうしても追加の作業が必要になることがあるんです。そして、その作業には、当然料金がかかってきます。
これは、決して業者が意地悪で請求しているわけではなく、作業員の方の手間や時間、専門的な技術に対して支払う、正当な「費用」です。ただ、問題は、それを事前にきちんと説明してくれるかどうか。
優良な業者さんは見積もりの段階で「お客様の場合、〇〇の作業が必要なので、追加で〇円かかります」と正直に教えてくれます。一方で、残念ながら、当日になってから「これも追加です」と言い出す業者さんもいるのが現実です。
ここでは、そんな「聞いてないよ!」を防ぐために、特に発生しやすい3つの追加料金について、私の経験も交えながら詳しくお話ししますね。
1-4-1. 階段料金:エレベーターなし3階はいくら?

これは、エレベーターがない建物で、2階以上の部屋から荷物を運び出す場合にかかる料金です。考えてみれば当然で、重いタンスや冷蔵庫を階段で運ぶのは、平らな場所を運ぶのとは比べ物にならないくらい大変な作業ですからね。
私の父の家は、幸い一軒家だったのでこれは関係ありませんでしたが、以前に友人がアパートの3階から引っ越す時に、この料金がかかっていました。
料金の相場としては、「1フロア上がるごとに、総額にプラス〇円」という計算方法が多いようです。
- 2階:3,000円~5,000円
- 3階:5,000円~8,000円
くらいが目安でしょうか。業者さんによっては「作業員1人につき〇円」と、人数で計算するところもあるようです。
もし、ご自宅がエレベーターなしの2階以上なら、見積もりを頼む時に「うちはエレベーターがない3階なんですが、階段料金はかかりますか?かかるとしたら、総額でいくらですか?」と、最初に必ず確認しておきましょう。
1-4-2. 解体作業費:このベッド、解体しないと出せないかも?
組み立て式の大きなベッドや、壁一面のシステム家具。買った時は部屋の中で組み立てたけれど、いざ運び出すとなると、ドアや廊下を通らない…。そんな時に必要になるのが、家具の「解体作業」です。
これも、ただネジを外せばいいという単純なものではなく、安全に運び出せるように考えながら分解する、専門的な技術です。そのため、基本料金とは別に費用がかかることがほとんどです。
料金は、解体する家具の種類や大きさによって変わりますが、
- ベッドフレームの解体:3,000円~8,000円
- 大きな食器棚やタンスの解体:5,000円~15,000円 くらいを見ておくと良いかもしれません。
これも、当日になって「このままじゃ運び出せないので、解体しますね。追加で〇円です」と言われると、断るに断れませんよね。ご自宅に解体が必要になりそうな家具がある場合は、見積もりの段階で「このベッド、解体しないと出せないと思うんですが、作業費はかかりますか?」と、こちらから先に聞いてしまうのが一番安心です。
解体日について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください
1-4-3. スタッフ増員費:「作業員1名」プランの落とし穴
広告で見た「5万円」という料金。実はこれ、「作業員1名で伺った場合の料金」になっていることがあるので、注意が必要です。
考えてみてください。2トントラックいっぱいの荷物を、たった一人で運び出すのは、物理的に不可能です。大きなタンスや冷蔵庫は、一人では絶対に運べませんよね。
つまり、大量の不用品を回収してもらう場合は、作業員が2名以上いることが大前提になります。
それなのに、基本料金を安く見せるために、広告では「作業員1名」の料金を載せておいて、見積もりや当日の段階で「お客様の荷物量ですと、作業員がもう一人必要なので、追加で15,000円かかります」と言われるケースがあるのです。
これは、もう「そういうやり方なんだな」と思うしかありません。だからこそ、私たちが自分を守るためにできるのは、最初の電話やメールの段階で、「その料金は、作業員さん何名でのお値段ですか?」と確認すること。そして、「うちの荷物量だと、何名で来てもらえるんですか?」と、はっきり聞いておくことです。
誠実な業者さんなら、荷物の量を伝えれば「それでしたら、2名でお伺いして、総額で〇万円になります」と、正直に答えてくれるはずですよ。
1-5. 「うちの場合」の正確な料金を知るための、ズル賢い見積もり術
さて、ここまでトラックの容量や、いろんな追加料金についてお話ししてきました。これまでの話で、ただ電話して「2トントラック一台、いくらですか?」と聞くだけでは、全く意味がないことがお分かりいただけたと思います。
大事なのは、「我が家のこの状況で、全部片付けてもらうには、最終的にいくらになりますか?」という、「我が家だけの正確な金額」を知ることです。
そのために必要なのは、業者さんとのちょっとした駆け引き。いえ、駆け引きと言うと聞こえが悪いですね。「自分のお家の状況を、いかに正確に業者さんに伝え、あいまいな見積もりを出させないようにするか」という、自分を守るための、少しだけ賢い技術です。
1-5-1. 見積もり時に伝えるべき「魔法の言葉」とは

さて、いよいよ見積もり金額を出してもらう、という最終段階。ここで、ただ「いくらですか?」と聞くのではなく、最後にダメ押しで添えるべき「魔法の言葉」が3つあります。これを言うだけで、相手の業者さんは「お、このお客さんは詳しいな。下手なことは言えないな」と思ってくれるはずです。
魔法の言葉①:「この金額は、当日に追加料金が発生しない『確定料金』と考えていいですか?」
これは一番大事な言葉です。あいまいな「概算の見積もり」ではなく、「これ以上はかからない、確定した金額ですか?」と念押しすることで、当日の「聞いてないよ!」という追加請求をほぼ防ぐことができます。もし、例外的に追加料金が発生する可能性があるなら、誠実な業者ならこの時点で「〇〇の場合だけは、別途かかります」と説明してくれるはずです。
魔法の法②:「ちなみに、もし荷物が乗り切らなかった場合の追加料金のシステムも、念のため教えていただけますか?」
「確定料金」と聞いた後で、さらにこう質問します。これは、「万が一の事態も、ちゃんと考えていますよ」という意思表示です。この質問をすることで、万が一荷物がオーバーしても、法外な追加料金を請求されるリスクを減らすことができます。
魔法の言葉③:「その金額は、作業員さん何名でのお値段ですか?」
前の章でお話しした、「作業員1名プランの落とし穴」を回避するための言葉です。この質問で、料金に人件費がきちんと含まれているかを確認できます。「2名でお伺いして、この金額です」という言質を取っておけば、当日になって「人を増やしたので追加です」とは言えなくなります。
私が実家の片付けで最終的にお願いした業者さんは、これらの質問に、一つ一つ丁寧に、嫌な顔一つせず答えてくれました。このやり取りを通じて、「あ、この会社は信頼できるな」と確信できたのを覚えています。
これらは、業者さんを困らせるための意地悪な質問ではありません。お互いが気持ちよく作業を進めるための、大事な確認作業なのです。
第2章:回収当日、私は何をすればいい?準備から完了報告までの完全シミュレーション

いよいよ回収業者さんが来る日。見積もりも完璧、業者さん選びも大丈夫。でも、当日になって「あれ、これどうしよう?」とバタバタしてしまうのは避けたいものですよね。
当日の朝、お茶を一杯飲むくらいの余裕を持つために。そして、何よりも「あ、あれも持っていかれちゃった!」という一番悲しい後悔をしないために。前日までにできる「準備」と「心構え」が、実はとても大切なんです。
ここからは、私が実際に「これはやっておいて本当に良かった!」と感じた、具体的な準備の方法をお伝えします。
2-1.【前日までの準備編】後悔しないための「仕分け」と「心構え」
当日の作業をスムーズに進めるカギは、業者さんが来る前に、こちら側で「回収してもらう物」と「残しておく物」を、はっきりと分けておくことに尽きます。
2-1-1. タンスの中身、そのままでOK?業者に聞かれる前に知っておきたいこと
これ、私もすごく迷いました。父の洋服ダンスに入っている古い服や小物、これって全部出しておくべきなの?と。
結論から言うと、「タンスや棚の中身が、すべて不用品なら、そのままで大丈夫」な場合が多いです。業者さんは、タンスを丸ごと「不用品」として運び出してくれますからね。
ただし、いくつか注意点があります。
- 食器棚の食器、本棚の本:これらは、運ぶ時に中でガチャガチャ動いたり、重すぎて棚板が抜けたりする危険があるので、できれば事前に箱詰めしておくのが一番丁寧です。業者さんによっては「そのままで大丈夫ですよ」と言ってくれることもありますが、作業の安全と効率を考えると、出しておいた方が親切かな、と私は思います。
- 中に残しておきたい物が少しでもある場合:これは絶対に、全部出してください。「この一番下の段のアルバムだけ残して、あとは全部捨ててください」なんていうお願いは、当日の混乱のもと。間違いが起こる最大の原因になります。
一番大事なのは、業者さんが「このタンスは、中身も含めて丸ごと持っていっていいんですね?」と聞いた時に、「はい、お願いします!」と、迷いなく即答できる状態にしておくことです。
2-1-2.「これは捨てないで!」大切なものを守るための鉄壁ガード術
さて、ここが一番、一番大事なポイントです。 不用品回収で最も悲しいトラブルは、お金のことよりも何よりも、「捨てたくなかった大切な思い出の品まで、間違って持っていかれてしまった」ということ。
これだけは、絶対にあってはなりません。そのために、私が実践した「鉄壁のガード術」はとても簡単です。
それは、「残しておきたい物は、不用品を置いてある部屋から、完全に別の部屋に移動させておく」こと。
「この棚は残します」と口で言ったり、付箋を貼ったりするだけでは、当日の忙しい作業の中では見落とされてしまう可能性があります。だから、物理的に場所を分けてしまうのが、一番確実で安全なんです。
私の場合、実家の一室(父の寝室でした)を「残すもの部屋」と決め、そこに
- アルバムや古い手紙
- 父が大切にしていた万年筆
- 母の形見の小さなアクセサリーケース
などを、すべて運び込みました。そして、作業が始まる前に、業者さんに「この部屋にあるものは、絶対に触らないでください」と、はっきり伝えました。こうすれば、間違いは絶対に起こりません。もし一部屋確保するのが難しければ、お風呂場やトイレなど、作業員の方が入らない場所にまとめておくのも良い方法です。
2-1-3. 捨てるか迷う「グレーゾーン」の不用品、一時保管場所の作り方
片付けをしていると、必ず出てきますよね。「捨てるのは忍びないけど、かといって取っておく場所もない…」という、判断に迷う「グレーゾーン」の物たち。
当日に業者さんを目の前にして、「うーん、これはどうしよう…」と悩んでいる時間はありません。作業が滞ってしまいますし、焦って「ええい、もうこれも捨てちゃえ!」と後悔の元になる決断をしてしまいがちです。
だから、そういった「迷う物」は、前日までに一つの箱や袋にまとめておくことをお勧めします。そして、その箱は「残すもの部屋」に一時的に置いておくのです。
そうすれば、当日は迷わず「回収する物」だけを業者さんにお願いできます。そして、すべての片付けが終わって落ち着いてから、その「迷い箱」の中身と、もう一度ゆっくり向き合えばいいのです。私の経験上、一日置いて冷静になると、「やっぱりこれはもういいかな」と、すんなり手放せるものが多かったですよ。
2-1-4. 貴重品はどこに隠す?当日の置き場所ベスト3
最後に、現金や通帳、印鑑、貴金属といった、いわゆる「貴重品」についてです。
もちろん、信頼できる業者さんを選んでいるはずですが、それでも万が一のことを考えて、貴重品は作業員の方の目に触れない場所に、きちんと保管しておくのが大人のマナーです。
「どこに置いておけば安心?」と考えた時、私のおすすめは以下の3つの場所です。
- ベスト①:自分のカバンの中に入れて、常に身につけておく これが一番安全で確実です。ショルダーバッグなどに入れて、作業中もずっと持っておけば、心配事は何もありません。
- ベスト②:車の中に置いておく もしご自宅に車があるなら、ダッシュボードなどに入れて鍵をかけておけば安心です。
- ベスト③:「残すもの部屋」の、さらに奥に隠しておく 「残すもの部屋」のクローゼットや押し入れの中など、さらに一段階奥まった場所に置いておくのも良いでしょう。
当日は人の出入りも多く、家のドアも開けっ放しになる時間が長くなります。業者さんを疑う、というわけではなく、防犯上のリスク管理として、自分の大切なものは自分でしっかりと守る。この心構えが、当日の余計な心配をなくしてくれます。
2-2.【作業開始編】業者が来たら、まず何をチェックする?
ピンポーン、とチャイムが鳴り、いよいよ作業が始まります。笑顔で「おはようございます!」と挨拶を交わした後、すぐに「では、お願いします」と作業を始めてもらう…のは、少しだけ待ってください。
実は、作業が本格的に始まる前の「最初の5分間」が、その日一日をスムーズに進めるために、そして「こんなはずじゃなかった」を防ぐために、非常に重要なんです。ここで確認すべきことは、たった3つだけです。
2-2-1.「養生」はしてくれる?マンションの共用部と室内の必須確認ポイント
まず、業者さんが家に入ったら、作業を始める前に、床や壁を保護するシートやマット(「養生(ようじょう)」と言います)を敷いてくれるか、そっと見てみましょう。
丁寧で経験豊富な業者さんは、こちらが何も言わなくても、大きな家具を運び出す動線上に、手際よくこの養生をしていきます。これは、「お客様の大切な家に傷をつけません」という、プロとしての意思表示のようなものです。
私の友人が別の業者に頼んだ時、この養生を全くしてくれず、案の定、運び出しの際に床に大きな引きずり傷がついてしまった、という話を聞いたことがあります。後の祭りにならないよう、以下のポイントは必ずチェックしてください。
- 室内で確認する場所:不用品が置いてある部屋から、玄関までの床。特に、何度も人が通る廊下や、家具を曲がる時にぶつけやすい壁の角など。
- マンション・アパートの場合:自分の部屋の中だけでなく、玄関ドアの外の廊下や、エレベーターの中も確認しましょう。共用部は、他の住民の方も使う場所。ここに傷をつけてしまうと、後々大きなトラブルになりかねません。
もし、作業員の方が養生を始める気配がなかったら、「すみません、床や壁の養生はお願いできますか?」と、遠慮なく、でも丁寧に伝えて大丈夫です。これは、私たちの正当な権利ですからね。
2-2-2. 作業員は何人来た?大量の荷物をスムーズに運び出すための適正人数

次に確認したいのが、「今日、作業してくれるのは何人ですか?」ということです。
第一章でお話しした通り、2トントラックいっぱいの大量の荷物を運び出すには、最低でも2名の作業員さんがいなければ、安全かつスムーズには進みません。見積もりの段階で、「2名で来ます」という約束になっているはずです。
当日、もし約束より少ない人数しか来ていなかったら、それは要注意のサインかもしれません。人数が少ないと、作業時間が長引くだけでなく、無理な運び方をして家や家具を傷つけたり、作業員さん自身が怪我をしたりするリスクも高まります。
リーダー格の方に、「お見積もりの時は2名と伺っていましたが、今日は何名で作業していただけますか?」と、あくまで「確認」という形で聞いてみましょう。もし、やむを得ない事情で人数が減ってしまった場合でも、誠実な業者さんなら、その理由と今後の進め方をきちんと説明してくれるはずです。
2-2-3. 見積書と最終確認!「聞いてない」を防ぐための念押しトーク
そして、これが一番大事な最終確認です。 荷物を一つでも動かし始める前に、手元に用意しておいた見積書を見せながら、責任者の方と最終的な打ち合わせをします。
私の実家の片付けの時も、作業前にリーダーの方と一緒に、捨てる物と残す物を指差し確認しました。そのおかげで、私が「残すもの部屋」に入れ忘れていた小さな棚を、「あ、それは残す物です!」と気づくことができたんです。あの時確認していなかったら、きっとそのまま持っていかれていました。
この最後のひと手間が、お互いの認識のズレをなくし、トラブルを防ぎます。以下の2つの言葉を、ぜひ使ってみてください。
- 確認トーク①(金額について):「こちらが先日いただいたお見積書ですが、本日のお支払いは、この金額でお間違いないでしょうか?」
- 確認トーク②(作業内容について):「それでは作業の前に、お手数ですが、回収していただく物を一緒に確認していただいてもよろしいですか?」
これは、業者さんを疑っているわけでは決してありません。「お互いに気持ちよく仕事を進めるための、最終確認ですね」という姿勢でお願いすれば、プロの業者さんなら快く応じてくれます。この確認が終われば、あとはもう安心。プロの仕事にお任せしましょう。
2-3.【作業中編】私はどこにいればいい?お任せと指示出しのベストバランス
さて、いよいよ本格的な運び出し作業が始まりました。テキパキと動く作業員の方々を横目に、「私は何をしてればいいんだろう…」と、手持ち無沙汰になってしまう。これ、経験者なら「あるある!」と頷いてしまう、意外な悩みどころですよね。
ずっと監視するのも失礼だし、かといって別室にこもってしまうのも無責任な気がする…。
この時間帯の私たちの役割は、「作業の邪魔はしない。でも、質問されたらすぐに答えられる場所にいる」ことです。この絶妙な距離感を保つことが、結果的に作業をスムーズに進める一番の近道なんですよ。
2-3-1. 飲み物の差し入れは必要?タイミングとスマートな渡し方
まず、多くの方が悩むのが「飲み物の差し入れ」問題。私も「こういうのって、渡した方がいいのかしら?」と、すごく迷いました。
結論から言うと、絶対に必要というわけではありません。 用意しなかったからといって、作業が雑になるなんてことは絶対にありませんので、安心してください。あくまで「感謝の気持ち」なので、無理のない範囲で考えれば大丈夫です。
もし「お疲れ様です、という気持ちを伝えたいな」と思ったら、以下のポイントを参考にしてみてください。
- 何を渡す?:ペットボトルや缶に入ったお茶やスポーツドリンク、お水などが一番喜ばれます。夏なら冷たいもの、冬なら温かいものを用意できると、さらに気が利いていますね。ポイントは、相手が好きな時に飲めて、持ち運びもしやすい蓋つきの飲み物を選ぶことです。
- いつ渡す?:タイミングが一番大事です。作業が始まった直後や、終わり際のバタバタしている時は避けましょう。おすすめは、作業が始まって1時間くらい経ち、キリのいいタイミング(一部屋片付いた、大きな家具を運び終えたなど)で、少し休憩を取っている時です。
- どう渡す?:ここが一番のポイントです。「さあ、飲んでください!」とその場で手渡すのは、相手に気を遣わせてしまい、かえって作業を中断させてしまうことも。一番スマートな渡し方は、こうです。
「お疲れ様です。よかったら、休憩の時にでも飲んでください。ここに置いておきますね」
こう言って、玄関の隅や廊下の邪魔にならない場所に、人数分を袋などに入れて置いておく。これなら、作業員さんたちは自分の好きなタイミングで手に取ることができます。このちょっとした気遣いが、お互いの気持ちを和ませてくれますよ。
2-3-2. 作業がスムーズに進む「神様みたいなお客様」と思われる立ち回り術
飲み物の差し入れ以上に、業者さんが「このお客さん、ありがたいな…」と感じるのは、私たちの当日の「立ち回り方」です。プロの方々が気持ちよく、かつ効率的に仕事を進められるように、私たちができる簡単なコツがいくつかあります。
- いる場所は「すぐ声が届く、邪魔にならない場所」 一番良いのは、リビングやキッチンなど、作業している部屋のすぐ近くの部屋で、静かに自分の作業(読書や簡単な片付けなど)をしていることです。これなら、作業の邪魔になることも、監視しているような威圧感を与えることもありません。そして、何か確認したいことがあった時に、業者さんがすぐに声をかけられます。
- 一番の「お手伝い」は、手を出さないこと 重い物を持っているのを見ると、つい「私も持ちます!」と言いたくなりますが、これはぐっと我慢。素人が下手に手伝うと、かえって運び方のバランスが崩れて危険ですし、怪我の元です。プロの仕事は、プロに安心してお任せする。 これが、一番の信頼の証です。
- 最高の「神対応」は、「即答」できる準備をしておくこと 作業中、業者さんが一番困るのは、判断に迷う物が出てきた時に、私たちの返事を待たなければいけない時間です。 「奥様、この棚の奥にある小さな箱も、処分でよろしいですか?」 と聞かれた時に、「えーっと、どうしようかしら…」と悩み込んでしまうと、その間、作業員さんの手は止まってしまいます。
前の章でお話しした「捨てる物」と「残す物」の仕分けが完璧にできていれば、どんな質問にも「はい、お願いします」「いいえ、それは残します」と、即答できるはずです。
私の実家の片付けの時も、リーダーの方が何度か「これはどうしますか?」と聞きに来てくれましたが、すべて迷わず即答できたことで、作業が本当にスムーズに進みました。「お客様が迷わないでくれるのが、一番仕事が早いです」と、最後に言っていただけました。
私たちができる最高のお手伝いは、明確な「指示」を、すぐに伝えられるように準備しておくこと。 これに尽きるのです。
2-4.【ご近所への配慮編】お互い気持ちよく!トラブル回避の鉄則

自分の家の中がスッキリ片付いて嬉しい、でも、その作業のせいでご近所さんに迷惑をかけてしまったら…。後から気まずい思いをするのは、他でもない私たちです。
特に、2トントラックのような大きな車が家の前に停まり、たくさんの荷物を運び出すとなると、どうしても普段よりは周りに影響が出てしまいます。
でも、ほんの少しの事前準備と「お互い様」の気持ちを伝えるだけで、トラブルはほぼ100%防げます。ここでは、私が「これはやっておいて良かった」と心から思った、ご近所への配慮のポイントを具体的にお話ししますね。
一軒家の不用品処分ならこちらの記事も参考になります!
2-4-1.「トラックが邪魔!」と言われないための駐車スペースの事前確認と交渉術
一番のトラブルの元になりやすいのが、トラックの駐車問題です。家の前の道が狭かったり、交通量が多かったりすると、なおさらです。
まず、見積もりをお願いする段階で、業者さんに「うちの前の道、これくらいの広さなんですけど、トラックは停められますか?」と、正直に伝えておくことが大切です。可能なら、家の前の道路の写真を撮って送っておくと、業者さんも状況が分かって安心です。
その上で、当日までに私たちでできることが2つあります。
- ① 自宅の駐車スペースを空けておく もしご自宅に駐車場があるなら、その日は朝から自分の車を別の場所(近くのコインパーキングなど)に移動させて、業者さんのトラックのためにスペースを空けておくのが一番確実で、最もスマートな方法です。
- ② どうしても路上に停めるしかない場合 家の前に停めるしかない場合も、もちろんありますよね。その時は、ただ業者さん任せにするのではなく、お隣の家の車の出入りに邪魔にならないか、曲がり角を塞いでしまわないか、といった点を私たち自身の目で確認しておくことが大事です。もし、お隣の玄関や駐車場の真ん前に停めることになりそうなら、次の「挨拶」の時に、そのことを一言伝えておくだけで、相手の心証は全く違ってきます。
業者さんもプロなので、できるだけ邪魔にならないように停めてくれますが、最終的な責任は依頼した私たちにある、という気持ちでいることが大切です。
2-4-2. 騒音と作業時間、ご近所には「いつ・何を・どう伝える」のが正解?
次に気になるのが、作業中の音や人の出入りですよね。静かな住宅街だと、トラックのエンジン音や、家具を運ぶ音は意外と響くものです。
一番良いのは、前日か当日の朝に、両隣とお向かいの3軒くらいに、直接顔を合わせて挨拶しておくことです。遠くまで知らせる必要はありません、日頃から顔を合わせる範囲だけで十分です。
でも、何をどう伝えればいいか、迷いますよね。ポイントは、難しく考えず、シンプルに伝えることです。
伝えるべきこと
- いつ:「今日の(明日の)〇時頃から〇時頃まで」
- 何を:「家の片付けで、業者のトラックが来ます」
- お願い:「少しご迷惑をおかけするかもしれませんが、すみません」
これを、丁寧な言葉で伝えるだけです。例えば、こんな感じです。
「こんにちは、お隣の鈴木です。実は、今日の午前10時から2時間ほど、家の片付けで業者が来ることになりまして。トラックが家の前に停まったり、少し人の出入りでご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします」
これだけで十分です。高価な手土産などは全く必要ありません。むしろ、相手に気を遣わせてしまいます。「事前にわざわざ知らせてくれた」という、その気持ちが何よりも大切なのです。
2-4-3. マンションの管理人さんへの挨拶、忘れていませんか?
これは、特にマンションやアパートにお住まいの方に、絶対に忘れないでほしいポイントです。
マンションには、住民みんなが気持ちよく暮らすための「ルール」があります。業者が出入りする際は、事前に管理組合や管理人さんに届け出が必要な場合がほとんどです。
これを怠ってしまうと、後から管理人さんに注意されたり、最悪の場合、他の住民の方とのトラブルに発展したりする可能性もあります。
不用品回収の日程が決まったら、できるだけ早く管理人さんに、
- 作業の日時
- 依頼した業者の名前
- 作業内容(不用品回収であること) を伝えて、必要な手続きがないか確認しておきましょう。
管理人さんは、いわばマンションの「顔」。きちんと筋道を通しておくことで、当日の作業もスムーズに進みますし、何より私たち自身が、余計な心配をせずに片付けに集中できます。
たかが挨拶、されど挨拶。この少しの手間が、面倒なご近所トラブルを防ぐ、一番効果的なお守りになるのです。
2-5.【作業完了編】トラックを見送る前に、絶対に確認すべきこと
「終わりましたー!」という業者さんの声。山のようにあった不用品がきれいになくなった部屋を見て、思わず「わー、ありがとうございます!」と、ホッと胸をなでおろす瞬間ですよね。
ですが、お金を払ってトラックを見送るのは、最後の「確認作業」が終わってからです。これをやらずに後から「あれ?」と気づいても、もう遅いかもしれません。気持ちよく一日を締めくくり、後味の悪い思いをしないために、最後の5分間だけ、もう一度気を引き締めましょう。
2-5-1. 部屋に傷はない?追加料金は発生していない?最終チェックリスト
すべての荷物がトラックに積み込まれたら、責任者の方と一緒に、部屋の中をぐるっと一周見て回ります。これは、向こうから「ご確認ください」と言ってくれることがほとんどですが、もし言われなくても、こちらから「最後に中を確認させていただいてもいいですか?」とお願いしましょう。
その時にチェックするのは、以下の3つのポイントです。
- ① 回収忘れはないか? 「これもお願いしたはずなのに…」という物が、部屋の隅に残っていないか、最終確認します。
- ② 床や壁に、新しい傷がついていないか? これが一番大事です。養生をしてもらっていても、たくさんの家具を運び出せば、どうしても傷がつくリスクはあります。作業前に「なかったはずの傷」がついていないか、特に家具を運び出した動線(廊下や壁の角、玄関周りなど)を重点的にチェックします。もし傷を見つけたら、その場ですぐに責任者の方に伝えましょう。誠実な業者さんなら、加入している保険などで、きちんと対応してくれるはずです。
- ③ 最終的な請求金額は、見積書通りか? 会計の前に、見積書の金額と請求されている金額が同じかどうか、自分の目でしっかりと確認します。もし、何らかの追加料金が発生している場合は、その「理由」と「内訳」を、きちんと説明してもらいます。「何となく高くなっている」というような、あいまいな状態でお金を払うのだけは、絶対にやめましょう。
私の場合は幸い、傷もなく、見積もり通りの金額でしたが、この最終確認を一緒にやったことで、「お互いに納得して、気持ちよく終われたな」という安心感がありました。
2-5-2. 領収書は必ずもらう!その後のトラブルに備えて
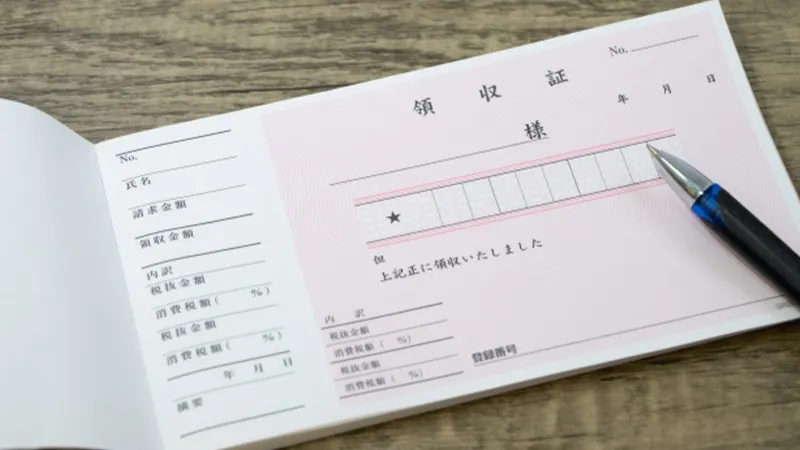
金額に納得し、お金を支払ったら、最後に必ず「領収書」をもらってください。
「もう終わったし、別にいらないかな」と思うかもしれません。でも、この一枚の紙が、後から何かあった時の、私たちを守る唯一の「証拠」になります。
例えば、
- 後日、回収してもらったはずの物が近所に不法投棄されていた(悪質な業者の場合、稀にあります)
- 後から家の傷に気づき、業者に連絡する必要が出た
といった、万が一のトラブルの際に、「いつ、誰が、いくらで、どんな作業をしたのか」を証明してくれるのが、この領収書です。
会社名、住所、電話番号、そして作業内容がきちんと書かれているかを確認して、受け取ってください。レシートのような簡易的なものではなく、できればちゃんとした領収書を発行してもらうのがベストです。
「領収書、いただけますか?」 このひと言を、絶対に忘れないでください。
これですべての作業が完了です。 トラックが見えなくなるまでお見送りをして、静かになった部屋に戻る。少し寂しいような、でも、目の前がパッと開けたような、清々しい気持ちになるはずです。
大変な作業、本当にお疲れ様でした。 このメディアが、あなたの「スッキリ」への第一歩を、少しでも後押しできたなら、これ以上に嬉しいことはありません。
おわりに
最後までこの記事にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
「2トントラック」「不用品 大量」――。 この記事を読み始める前、あなたはこの言葉に、どこか途方もない、漠然とした不安を感じていたかもしれません。「一体いくらかかるんだろう」「どんな人が来るんだろう」「面倒なことになったらどうしよう」。
しかし、ここまで読み進めてくださった今のあなたはどうでしょう。 トラックの容量の考え方、隠れた追加料金の種類、そして業者さんとの賢い付き合い方。たくさんの知識を身につけたあなたは、もう、ただ不安に思うだけのあなたではないはずです。ご自身の状況を冷静に判断し、自信を持って行動するための「ものさし」を、その手に持っているはずです。
私が父の家を片付け終えた後、がらんと広くなった部屋の真ん中で感じたのは、寂しさだけではありませんでした。そこには、不思議なほどの「清々しさ」と、「これで前に進める」という静かな安堵感があったのです。
たくさんの不用品を片付けるという作業は、単なる「モノの処分」ではありません。 溜め込んだ過去を整理し、空間だけでなく、心の中にも新しい「余白」を作るための、大切な時間なのだと思います。その余白に、これからどんな新しい思い出を置いていきますか。どんな心地よい時間を流していきますか。
それは、これからの暮らしを、もっと心地よく、もっと自分らしく整えるための、大切な、大切な一歩です。
さあ、次はあなたの番です。 この記事が、その大きな一歩を踏み出すための、信頼できる地図のような存在になれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。
あなたの「スッキリ」した未来を、心から応援しています。